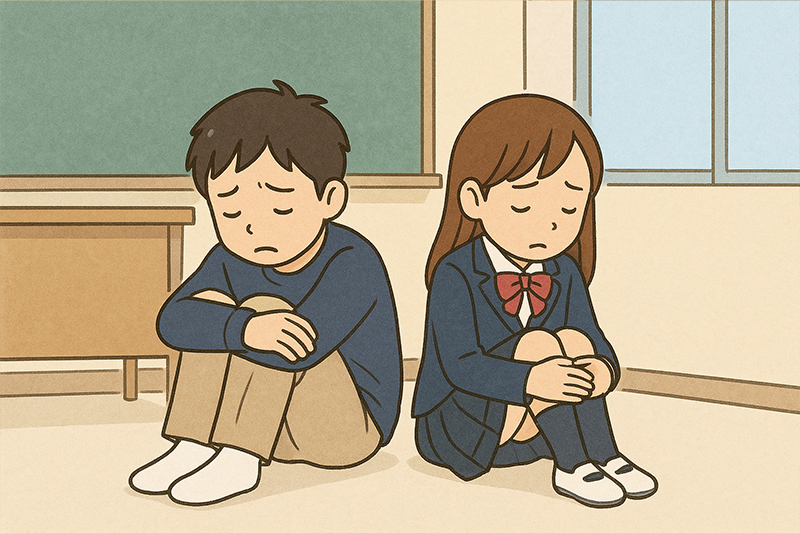
不登校の男女差とは?データで見る現状
文部科学省が公表している不登校調査によると、男女の不登校児童生徒数には明確な差があります。全体で見ると、男子がやや多い傾向にあります。特に中学生では男子の割合が高く、高校になるとやや均等に近づく傾向が見られます。
男子は「学校の雰囲気になじめない」「学習意欲がわかない」といった理由が多く、女子は「人間関係の悩み」「身体の不調」が背景にあるケースが多いことも報告されています。つまり、男女では「学校生活の中で感じるストレスの種類」が異なるのです。
また、小学生段階では男女差が比較的少ないものの、思春期を迎える中学生以降に差が広がる傾向があり、心身の変化や人間関係の影響がより強く関与していると考えられます。
男子の不登校に多い特徴と背景
学業や評価へのプレッシャー
男子の不登校では、学力や成績に対するプレッシャーが背景にあるケースが少なくありません。特に「できない自分を見せたくない」「失敗を恐れる」といった完璧主義的な思考が、登校への抵抗感につながることがあります。
感情表現が苦手で、怒りや沈黙で表す傾向
男子は感情を言葉で表現することが苦手な傾向があります。辛さや不安を「怒り」「無言」などで表すことも多く、親が「反抗的」と受け取ってしまう場合もあります。しかし、これは防衛的な反応であり、内面には「認められたい」「理解してほしい」という思いが隠れています。
ゲーム・ネットへの没頭
現実から逃れるように、オンラインゲームや動画視聴にのめり込むケースもよく見られます。ゲームの世界は「努力が報われる」「人間関係が単純」など、学校生活で得られない安心感を与えることがあります。ただし、それを過度に否定すると逆効果になるため、親は「本人の居場所」を否定しない姿勢が大切です。
女子の不登校に多い特徴と背景
人間関係トラブルが大きな要因
女子の不登校の多くは、友人関係に起因しています。仲間外れ、SNSでのトラブル、グループ内の上下関係など、目に見えにくい人間関係のストレスが心を蝕んでいきます。特に思春期女子は「周囲と同じであること」に価値を置く傾向があり、集団から外れる不安が強いのです。
身体的な不調として現れやすい
女子の場合、心理的なストレスが頭痛・腹痛・倦怠感など、身体症状として現れることが多くあります。学校に行こうとすると体が動かない、吐き気がするといった形で表れるため、親は「怠けている」と誤解しないことが重要です。
他人への気遣いが強すぎる
女子は人の気持ちに敏感で、無意識に「相手を傷つけないように」と自分を抑える傾向があります。その結果、自分の本音を言えず、心が疲弊してしまうのです。「いい子」でいようと頑張るタイプほど、不登校になるリスクが高いといわれます。
男子と女子の「不登校理由」の違い
男子は外的要因に、女子は内的要因に影響を受けやすい傾向があります。男子の場合、部活や勉強、先生との摩擦など「環境との衝突」がきっかけになりやすいです。一方、女子は「関係性の疲れ」「心の消耗」といった内面のストレスが蓄積して不登校につながります。
ただし、近年はこの境界もあいまいになってきています。男子でも繊細な人間関係に悩むケース、女子でも進学や競争にストレスを感じるケースが増え、性別よりも「個々の特性」に応じた支援が求められています。
高校卒業支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「高校卒業支援プラン」は、不登校や引きこもりの方でも自分のペースで高卒資格を取得できるプログラムです。通信制高校を活用し、登校日数を抑えながら自宅での学習を進められ、教員免許を持つスタッフによる個別指導も受けられます。学習はレポート提出や動画教材、スクーリングを組み合わせて進め、必要に応じて大学受験対策も対応。資格取得や単位修得を柔軟に支援し、将来の進路の幅を広げます。自宅送迎や月額支払いにも対応しており、安心して学習を始められる環境が整っています。
支援・関わり方の違い
男子への関わり方:承認と行動のきっかけを
男子に対しては、「小さな成功体験」を積ませることが有効です。たとえば、「朝起きられたね」「一緒に食事できたね」といった行動を認めることで、自己肯定感が回復していきます。行動を焦らず、少しずつ「動けた実感」を増やす支援が大切です。
女子への関わり方:共感と安心の土台を
女子の場合、まずは「話を聴く」「共感する」ことから始めましょう。「そんなこと気にしなくていい」と励ますより、「それはつらかったね」と受け止める姿勢が回復への第一歩です。心が落ち着けば、自分から外へ出る意欲が芽生えます。
話を引き出すタイミングの違い
男子は感情を表に出しにくいため、直接的な質問よりも「雑談」や「共同行動」を通じて少しずつ本音を引き出します。女子は、安心できる関係ができると自然と話し出すため、親の聴く姿勢が鍵になります。
学校・支援機関ができるサポートの工夫
学校や支援機関も、性別による傾向を理解した対応が求められます。男子には体験型・活動型のプログラム(ボランティア、職業体験など)が効果的です。行動を通じて自信を取り戻しやすいためです。
女子には、少人数で安心できるグループや、同じ悩みを共有できる環境が有効です。話し合いや表現活動など、感情を言葉にする機会を持つことが回復を促します。
また、フリースクールや適応指導教室などでは、男女問わず「自分のペースで過ごせる」ことが最も重要です。性差を意識しすぎず、子どもが安心していられる環境づくりが基本となります。
回復までの道のりと親ができるサポート
男子の場合は、「行動の再開」に焦点を当てがちですが、まずは心の安定が前提です。小さな行動を評価しながら、「自分にもできることがある」と実感できるよう支えることがポイントです。
女子の場合は、心の整理や安心感が回復の鍵です。気持ちを話すことでエネルギーを取り戻すタイプが多いため、親は聞き役に徹しましょう。焦らず「家庭を安全基地」として支える姿勢が大切です。
どちらにせよ、性別よりも「一人の人間として向き合う」ことが本質です。比較や焦りは逆効果となるため、「その子のペース」を尊重しましょう。
まとめ:男の子・女の子、それぞれの「不登校」に寄り添うために
不登校には、男子と女子で異なる傾向があります。しかし、その根底にあるのは「生きづらさ」や「理解されたい気持ち」です。性別による特徴を理解することは大切ですが、それ以上に「この子は何に困っているのか」を丁寧に見つめることが大切です。
親が焦らず、受け止め、共に歩むことで、子どもは再び自分のペースで歩き出す力を取り戻します。不登校は「終わり」ではなく、「再スタートの準備期間」。その時間を、親子で大切にしていきましょう。







