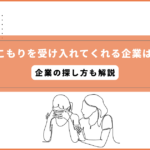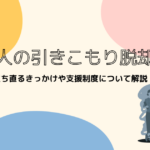「なぜうちの息子だけがひきこもってしまうの?」「どう接したらいいかわからない」「イライラして許せない気持ちになる…」
引きこもりの息子や娘に悩む親御さんは、現代の日本に数多くいらっしゃいます。
ひきこもりは本人だけでなく、周囲の家族、特に親にとって大きな苦しみとなります。「息子がひきこもって許せない」という感情を抱くことは、親として自然な反応なのです。
この記事では、息子のひきこもりの根本的な原因と、親御さんができる具体的な対策を詳しく解説します。
また、息子との接し方のポイントや、利用できる支援サービスも紹介しています。
引きこもり息子の実態と理解すべき心理状態
ひきこもりの息子を持つ親御さんが最初に直面するのは「なぜこうなったのか」という疑問です。息子の行動を理解するためには、まず引きこもりの実態と心理状態を知ることが重要です。
引きこもりの定義とは?厚生労働省による最新データ
引きこもりとは、厚生労働省の定義によれば「様々な要因の結果として、社会参加を回避し、原則的には6カ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態」を指します。(参照:ひきこもり評価・支援に関するガイドライン|厚生労働省)
2023年の内閣府の調査によれば、全国のひきこもり状態にある15歳から69歳の方は約146万人と推計されています。(参照:こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)|内閣府)また、「8050問題」と呼ばれる、80代の親が50代の引きこもりの子どもの生活を支える状況も社会問題となっています。
不登校と引きこもりの違いは何か?
不登校と引きこもりは、どちらも社会的な活動から離れるという点では似ていますが、異なる概念です。
不登校と引きこもりの主な違い
- 不登校は学校に行かないことに焦点が当たっている
- 引きこもりは社会参加全般の回避を指す
- 不登校は学齢期が中心だが、引きこもりは10代から50代以上まで幅広い
引きこもりの「本当の気持ち」とは
当事者への調査では、多くのひきこもりの方が「自分でも外に出たいと思っている」と答えています。しかし、「どうせ自分はダメだ」「また失敗するのではないか」という強い不安や恐怖から、一歩を踏み出せないことが多いのです。
ひきこもり当事者の声
- 「家族に迷惑をかけている罪悪感がある」
- 「社会に出たいけれど、どう動いていいかわからない」
- 「何をやっても失敗する気がして怖い」
なぜ息子は引きこもってしまったのか?5つの根本原因
息子がひきこもりになった原因を理解することは、適切な対応を考えるうえで非常に重要です。
心の病との関連性:見逃されがちなサインと症状
ひきこもり状態にある方の多くは、うつ病、社会不安障害、パニック障害、発達障害など、何らかの心の病を抱えていることが少なくありません。
見逃されがちなサインと症状
- 睡眠リズムの乱れ(昼夜逆転など)
- 食欲の変化(極端な増減)
- 趣味や好きなことへの興味の喪失
- 些細なことでイライラしたり、過剰に反応する
学校・職場での辛い経験:息子が話せない挫折
いじめや過度なプレッシャー、失敗体験など、学校や職場での辛い経験がひきこもりのきっかけになることがあります。特に男性は「弱みを見せたくない」という意識が強く、辛い経験を親にも打ち明けられないことが多いのです。
人間関係の難しさ:対人関係が苦手な理由
人間関係の構築に困難を感じる若者が増えています。発達障害があると、社会的なコミュニケーションのルールを直感的に理解することが難しく、集団に適応するのに苦労することがあります。
目標や希望の喪失:自信を失くした息子の心理
明確な目標や将来への希望を見失うと、「何のために頑張るのか」という根本的な動機が失われ、ひきこもりにつながることがあります。
目標や希望を失いやすいケース
- 過度な競争社会で自分の価値を見失う
- 理想と現実のギャップに絶望する
- 親や社会の期待に応えられないと感じる
専門家があなたの家族に寄り添います。

「部屋から出てこない」「会話が成り立たない」そんな日々に疲れていませんか?
まだ諦めるには早すぎます。
私たち『らいさぽセンター』は多くの引きこもりの若者たちとそのご家族に寄り添ってきました。

まずは、引きこもり支援の専門家にあなたの話を聞かせてください。
ひきこもり息子に悩む親に共通する5つの特徴と改善点
ひきこもりの息子を持つ親御さんには、時に共通した特徴や対応パターンが見られます。これらは無意識のうちに息子のひきこもり状態を長引かせてしまう可能性があります。
過度な干渉と保護:自立を妨げる親の行動パターン
多くの親御さんは、子どもを思う気持ちから「何とかしてあげたい」と考え、過剰に干渉したり保護したりする傾向があります。
過干渉・過保護の具体例
- 息子の生活の細部まで管理しようとする
- 小さな問題も親が先回りして解決してしまう
- 食事の用意から掃除まですべて親がやってしまう
息子が自分でできることは見守る姿勢を持ち、小さな成功体験を積み重ねられるよう環境を整えましょう。
世間体を気にしすぎる:専門家への相談をためらう理由
ひきこもりの問題に直面したとき、「近所の目が気になる」「親戚に知られたくない」といった世間体を気にするあまり、専門家への相談をためらう親御さんは少なくありません。
ひきこもりは特別なことではなく、誰の家庭でも起こりうる社会的な課題です。世間体よりも息子の幸せを優先しましょう。
会話の問題点:一方的な意見と聞く姿勢の欠如
親子間のコミュニケーションの問題もひきこもりの長期化に影響します。特に「親が一方的に話す」「息子の意見を聞かない」といったパターンは、息子の孤立感を深めてしまいます。
まずは息子の話を最後まで聞く姿勢を持ちましょう。アドバイスや意見を述べる前に、共感の言葉をかけることが重要です。
マイナス思考の家庭環境:愚痴や不満の悪影響
家庭内で愚痴や不満、否定的な発言が多い環境は、息子の心理状態に大きな影響を与えます。親自身がマイナス思考で物事を捉えると、息子も否定的な考え方を身につけやすくなります。
家庭内での会話をより肯定的なものに変えていきましょう。小さな成功や良いニュースを共有し、「できる可能性」に焦点を当てた会話を増やすことが大切です。
子どもへの依存と束縛:適切な距離感の必要性
親が子どもに過度に依存し、子どもの人生に自分の希望や夢を投影してしまうケースも見られます。「共依存」の関係は、息子の自立を難しくします。
親自身の生きがいや人間関係を大切にし、子どもとは適度な距離を保つことが重要です。
「息子が許せない」と感じる親の心理と向き合い方
引きこもりの息子を持つ親御さんが「許せない」と感じるのは自然な感情です。しかし、この感情をそのまま息子にぶつけると、状況は悪化する可能性が高いです。
許せない感情が生まれる理由
親が「許せない」と感じる背景には、様々な感情が複雑に絡み合っています。
- 期待とのギャップ:「こうなってほしい」という期待と現実のギャップ
- 無力感:何をしても状況が改善しないという無力感
- 将来への不安:息子の将来や自分たち老後の生活への不安
- 社会的な比較:他の家庭の子どもと比較する気持ち
怒りの感情とどう付き合うか
「許せない」という怒りの感情自体は悪いものではありませんが、その表現方法や対処法が重要です。
- 感情と行動を分ける:怒りを感じても、すぐに行動に移さない
- 別の場所で発散する:息子に直接ぶつけるのではなく、別の方法で発散する
- 怒りの根本原因を探る:何に対して怒りを感じているのかを具体的に言語化する
自分自身を責めすぎないために
引きこもりの原因を「親の育て方」に求め、自分を責め続ける親御さんも少なくありません。
- 複合的な要因を理解する:ひきこもりは親の育て方だけが原因ではない
- 「完璧な親」という幻想を手放す:すべての親は試行錯誤しながら子育てをしている
- 今できることに焦点を当てる:過去を悔やむよりも、現在の関係改善に力を注ぐ
親としての自己肯定感を高める方法
引きこもりの子どもを持つと、「親として失敗した」という自己否定感に陥りがちです。
- 小さな成功体験を認識する:息子との良好なコミュニケーションが取れた瞬間を意識的に記録する
- 自分の時間を大切にする:趣味や友人との交流など、親自身が楽しめる時間を確保する
- サポートネットワークを広げる:同じ悩みを持つ親の会に参加する
引きこもり息子を支える親が今日からできる7つの対応法
ひきこもりの息子に対して、親としてできることは少なくありません。今日から実践できる具体的な7つの対応法を紹介します。
安心できる居場所づくり:家庭内の温かい雰囲気作り
ひきこもりの息子にとって、家庭が「安心できる居場所」であることが何よりも重要です。
- リビングを開放的な空間にする
- 息子の好きなものを共有スペースに置く
- 食事の時間を大切にする
- 過度な期待や圧力をかけない
押しつけない会話術:息子の気持ちを尊重する話し方
コミュニケーションの質は、親子関係の改善において非常に重要です。
- オープンクエスチョンを使う
- 「聞く」ことに徹する時間を作る
- 共感のサインを示す
- 息子の意見を否定しない
親:「最近見ていたYouTubeの動画、面白そうだったね。どんな内容なの?」
子:「ああ、あれは○○について解説している動画で…」
親:「へえ、そうなんだ。詳しいんだね。もっと教えてくれる?」
医療の専門家への相談:適切な医療サポートの見つけ方
ひきこもりの背景には、うつ病や社会不安障害、発達障害など医学的なケアが必要なケースが少なくありません。
- まずはかかりつけ医に相談する
- ひきこもりに詳しい精神科・心療内科を選ぶ
- 受診のハードルを下げる工夫をする
- 必要に応じてオンライン診療を活用する
家族の足並みをそろえる:夫婦間の意見統一の重要性
父親と母親で対応が異なると、息子は混乱し、家庭内の緊張が高まります。
- 定期的な家族会議を開く
- 役割分担を明確にする
- 一貫した対応を心がける
- 非難の連鎖を断ち切る
親自身の心の健康を保つ:ストレス軽減のための習慣
息子のサポートを続けるためには、親自身の心身の健康を保つことが不可欠です。
親のセルフケア方法
- 自分の時間を確保する
- サポートグループに参加する
- 小さな成功を喜ぶ習慣をつける
- 必要に応じて親自身もカウンセリングを受ける
小さな成功体験の機会:自信を取り戻すきっかけづくり
ひきこもり状態から回復するためには、息子が「自分にもできる」という自信を取り戻すことが重要です。
実践できる具体策
- 得意なことや興味のあることを見つける
- 家庭内での役割を提案する
- スモールステップの設定をする
- 成功体験を言語化して伝える
長い目で見守る姿勢:焦らず寄り添う心構え
ひきこもりからの回復は一日で実現するものではありません。焦らず長い目で見守る姿勢が重要です。
長い目で見守るための心構え
- 進歩の定義を広げる(「就職」だけが成功ではない)
- 息子なりの回復のペースを尊重する
- 「待つ」ことの価値を理解する
- 希望を持ち続ける
引きこもりからの回復へ:効果的な支援サービスと成功事例
ひきこもりの問題は家族だけで解決するには限界があることも少なくありません。適切な外部の支援サービスを利用することが重要です。
専門的支援機関の選び方:5つの大切なポイント
支援機関は全国に数多くありますが、息子さんに合った機関を選ぶことが重要です。
支援機関選びのポイント
- 支援の対象年齢と内容の確認をする
- アプローチ方法(訪問支援の有無など)を確認する
- スタッフの専門性と経験を調べる
- 利用者や家族の評判を参考にする
- アクセスのしやすさと費用を考慮する
おすすめの就労支援サービス5選:特徴と活用法
就労支援サービスは、ひきこもり状態から社会参加を目指す際の強力な味方になります。
おすすめの支援サービス
- ひきこもり地域支援センター:都道府県・政令指定都市に設置された公的相談窓口
- 若者サポートステーション:15〜49歳の若者の就労を支援する国の機関
- 精神保健福祉センター・保健所:心の健康に関する専門的な相談窓口
- NPO法人・民間支援団体:独自の支援プログラムを持つ団体
- 就労移行支援事業所:一般就労に向けた訓練を行う障害福祉サービス
引きこもりの息子を持つ親御さんから寄せられる疑問に回答します。
ひきこもりは甘えですか?
回答: ひきこもりは「甘え」ではなく、様々な要因が複雑に絡み合った結果生じる状態です。うつ病や社会不安障害などの精神疾患や、発達障害などが背景にあることも多く、本人も苦しんでいます。責めるのではなく、原因を理解し適切なサポートを検討しましょう。
経済的援助はどこまでするべきですか?
回答: 経済的援助の範囲は家庭の状況や息子さんの年齢、状態によって異なります。基本的な生活費や治療費は保障しつつ、将来を見据えた自立を促す仕組みを考えることが大切です。家庭内での役割(家事分担など)を持つことも重要です。
長期間ひきこもっている息子でも回復できますか?
回答: はい、長期間ひきこもっていても回復は可能です。ひきこもり期間が5年、10年以上の方でも、適切な支援を受けることで社会復帰を果たした例は数多くあります。焦らず、小さな変化を大切にし、専門的な支援を活用しながら、本人のペースを尊重することが重要です。
兄弟姉妹への影響はどう対処すべきですか?
回答: オープンなコミュニケーションを心がけ、年齢に応じた説明を行いましょう。ひきこもりの息子だけに注目が集中しないよう、他の子どもにも十分な関心と時間を向けることが大切です。兄弟姉妹の気持ちを尊重し、過度な負担を背負わせないバランスが重要です。
親が高齢になった場合、息子はどうなりますか?
回答: 「8050問題」は多くの家庭が抱える課題です。早めに地域の福祉サービスや支援機関とのつながりを作り、障害年金や生活保護など利用できる制度の確認、将来の住まいの選択肢を探っておくことが大切です。自治体の福祉課や地域包括支援センターに相談することをお勧めします。
まとめ:息子さんも親御さんも、ともに幸せになるために
引きこもりの息子を持つ親御さんにとって、この問題は大きな苦しみをもたらすことがあります。しかし、適切な理解と対応、そして専門的な支援によって、状況が好転する可能性は十分にあります。
最後に大切なのは、親御さん自身も幸せになる権利があるということです。息子さんのことだけを考え、自分の生活や幸せを犠牲にしてしまうと、長期的には親子ともに疲弊してしまいます。
息子さんの自立を願うなら、まずは親御さん自身が自分の生活を充実させ、精神的にも肉体的にも健康を保つことが大切です。それが結果的に、息子さんの回復にもつながっていきます。