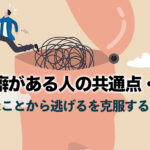ニートの多くは、親の扶養に入りながら生活をしているケースが多く、「収入がないから税金や社会保険は関係ない」「無職だから払う義務はない」と考えている方も少なくありません。
しかし実際には、たとえ働いていなくても、ニートや無職の立場であっても、住民税・国民年金・国民健康保険など、一定の条件下で支払い義務が発生することがあります。特に20歳以上の人には、国民年金の加入義務があるほか、扶養の範囲から外れている場合は、健康保険料や住民税の均等割なども負担対象となることがあります。
この記事では、無職・ニート状態の若年層に向けて、支払いが発生する可能性のある税金・社会保険の種類と、その金額の目安、親の扶養との関係、そして支払いが困難な場合に利用できる免除・猶予・減免制度の仕組みについて、わかりやすく解説していきます。無収入だからと放置せず、自分の立場に合った正しい知識を持つことが、将来の安心につながります。
「知らなかった」で損をしないために、まずは今の状況で知っておきたい制度や選択肢を一緒に確認していきましょう。
【引きこもりでも稼げる】自宅で安心・安全に稼ぐ方法5選|スキル不要・低ストレスな始め方ガイド
- ニートで支払う可能性のある税金・保険料
▶︎国民年金保険料・国民健康保険料・住民税・介護保険料・所得税 - 支払いができないときは
▶︎減免・猶予制度が活用できる場合がある - 税金・保険料の支払いを滞納すると…
▶︎延滞金が発生・督促状が届く・財産が差し押さえられることも - ニートでも確定申告が必要なケース
▶︎退職してニートになった場合・医療費が多くかかった場合・ふるさと納税をした場合など - 1年間無収入だった場合も、確定申告を行うと税金・保険料が減額されることがある
ニートが支払う可能性のある税金・保険料【一覧】

まずは、ニートが支払う可能性のある税金・保険料について、一覧でご紹介します。
| 税金・保険の種類 | 対象年齢 | 支払い義務 | 令和6年度 (2024年度) の金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 国民年金保険料 | 20~60歳未満 | 有り | 毎月16,980円 |
| 国民健康保険料 | 0〜74歳まで | 有り | 前年度の所得と 住んでいる地域により異なる |
| 住民税 | 18歳以上 | 有り | 【所得割】 前年度の所得により 異なる 【均等割】 5,500円 (地域によって異なる) |
| 介護保険料 | 40歳以上 | 有り | 前年度の所得によって決まる |
| 所得税 | 働いて収入のある人 | 無し | 収入がなければ発生しない |
それぞれの詳細については、次の章で詳しく解説していきます。
ニートが納める税金・保険料とは

それでは、ここからニートが納める税金・保険料について、それぞれ解説していきます。
国民年金保険料
国民年金保険料、いわゆる「年金」は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が対象となる公的年金制度です。
これは働いているかどうかに関係なく、学生や無職の人も含まれます。つまり、ニートであっても原則として保険料の支払い義務があるということです。
保険料は毎月決まった金額を納める必要があり、令和7年度(2025年度)は月額17,510円です。年間で考えると、約20万円の保険料を納めることになります。
また、国民年金の被保険者は、以下の3つに分類されます。
- 第1号被保険者
自営業(農業・漁業も含む)・学生・失業者など。納付書や口座振替を利用して納める。 - 第2号被保険者
会社員や公務員。厚生年金の適用となり、国民年金を個別で収める必要はない。 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている年収130万未満の人。支払いは、第2号被保険者が加入している厚生年金などが負担。
国民年金は、収入や生活状況に応じて、保険料の「免除制度」や「猶予制度」が利用できます。
免除や猶予が認められた場合、その期間も年金の受給資格期間としてカウントされるため、将来の年金額がゼロになることはありません。
年金の受給額は納付額によって変動するため、経済的に厳しいときこそ、未納にせず制度を活用することが大切です。
国民健康保険料
国民健康保険料は、会社などに勤めていない人が加入する医療保険制度です。
無職や自営業、アルバイトの人などが対象で、住んでいる市区町村の役所を通じて手続きします。
ニートであっても、親の扶養に入っていない場合は、自分で国民健康保険に加入し、保険料を納めなければなりません。
保険料を納めていれば、病院での診察や治療にかかる医療費のうち、自己負担する金額は原則3割で済みますが、未加入の場合は「全額自己負担」となるため注意が必要です。
保険料の金額は、前年度の所得や世帯の人数、住んでいる地域によって変わります。
そのため、現在収入がない場合でも、前年にアルバイトなどで収入があった場合や、世帯に収入のある家族がいる場合には、高額な保険料が請求されることがあります。
所得や生活状況に応じて保険料を減らす「減額制度」や「猶予制度」、分割での支払いにも対応しているため、支払いが難しい場合は、まずお住まいの市区町村の窓口で相談してみましょう。
住民税
住民税は、住んでいる市区町村と都道府県に納める地方税のことで、基本的には前年の所得に応じて課されます。
たとえば、今年は無職でも、昨年アルバイトや就職していた期間があり収入があった場合、その分に対して住民税がかかる仕組みです。
住民税は「所得割」と「均等割」の2つに分かれていて、所得が少ない場合でも一定額の均等割だけは請求されることがあります。
- 所得割:前年の所得に応じて決まる
- 均等割:所得の金額に関わらず一律で決まる
しかし、所得割・均等割どちらも非課税になるケースもあります。
- 生活保護を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4,000円未満)
- 自治体が決めた基準よりも収入が少ない など
上記に当てはまらない場合、均等割の支払いが必要になる、もしくは前年の収入が高ければ、思ったよりも高額な住民税の支払いが必要です。
請求が来たけれど支払いが難しい場合などは、市区町村の窓口で減免制度や分割払いが可能か相談してみましょう。
介護保険料(40歳以上)
介護保険は、40歳以上の人が加入する公的な保険制度です。
介護が必要な人を社会全体で支えることを目的とした保険制度で、介護サービスを利用した場合、費用の一部を保障してもらえます。
- 第1被保険者
65歳以上が対象。受給条件は、要介護状態・要支援状態にあること。
保険料は、原則年金から年引きされる。 - 第2被保険者
40〜65歳未満の医療保険加入者が対象。特定疾病(ガン・リウマチ・認知症など)による要介護・要支援状態にあること。
保険料は、加入している医療保険から徴収される。
40歳になると、自動的に介護保険の対象となり、保険料の支払いが始まります。
会社に勤めている人は給料から天引きされますが、無職や自営業、ニートの状態であっても、国民健康保険に加入していれば、その中に介護保険料も含まれるかたちです。
保険料の金額は、住んでいる地域や所得によって異なります。
収入が少ない場合は、介護保険料も減額の対象となることがあるため、経済的に厳しいときは、市区町村の役所で相談してみるのがおすすめです。
所得税
所得税は、働いて収入を得た人に対してかかる税金です。
会社員であれば給料から自動的に引かれ、アルバイトやパートをしている場合でも、収入に応じて所得税が差し引かれます。
一方、収入がまったくない状態であれば、基本的に所得税は発生しません。
つまり、ニートのように仕事をしていない人には、所得税の支払い義務はないということになります。
ただし、一時的にでもアルバイトなどで収入があった場合、その金額によっては所得税が発生することがあるため注意が必要です。
また、退社時期によっては、年末調整や確定申告をすることで、払いすぎた所得税が戻ってくることもあります。
専門家があなたの家族に寄り添います。

「部屋から出てこない」「会話が成り立たない」そんな日々に疲れていませんか?
まだ諦めるには早すぎます。
私たち『らいさぽセンター』は多くの引きこもりの若者たちとそのご家族に寄り添ってきました。

まずは、引きこもり支援の専門家にあなたの話を聞かせてください。
免除・減免・猶予制度

収入のないニートにとって、「支払い」は死活問題。
納税義務があると言われても、支払いが困難な人も多いのではないでしょうか。
そんな時は、税金・保険料の免除や減免・猶予制度の活用がおすすめです。
税金・保険料の免除・減免・猶予制度について、それぞれ詳しく解説します。
国民年金保険料の免除・猶予制度
国民年金保険料の支払いが難しい場合、免除または猶予の申請が可能です。
しかし、申請すれば必ず免除・猶予されるとは限らず、前年の所得や世帯主の所得などが審査対象となります。
現在収入がなくても前年の所得が高い場合や、実家暮らしをしている場合は審査が通らないということも少なくありません。
審査に通過した場合、免除される金額は、収入に応じて「全額・4分の3・半額・4分の1」から決定します。
また、20歳以上50歳未満の人で、前年所得が一定額以下の場合に利用できる納付猶予制度も設けられています。
免除・猶予制度を利用する場合に必要な書類は、以下のとおりです。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- マイナンバー、または基礎年金番号がわかるもの
- 失業を証明する書類(退職により納付が困難な場合)
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険受給資格通知
・雇用保険被保険者離職票
申請する場合は、役所の年金窓口や年金事務所に申請書を提出するか、郵送やオンラインでの申請も可能です。
注意するポイントとしては、免除・猶予制度を利用した場合、将来もらえる年金額は減額するということ。
受給する年金額を増やすには、免除・猶予後の追納が必要となるので覚えておきましょう。
国民健康保険料の減免制度
国民健康保険料も減免制度が利用できます。
適用条件は各市町村によって異なりますが、世帯全員の所得を合わせた上で、7割、5割、2割の減免率が決定される仕組みです。
そのため、実家で暮らしている場合は、減免額が低い、もしくは減免が受けられないケースがあります。
軽減基準の所得額は以下のとおりです。
| 軽減基準額 | 基準となる所得金額 |
|---|---|
| 7割 | 43万円+(10万円×(給与所得者の人数ー1)) |
| 5割 | 43万円+(28.5万円×被保険者数) +(10万円×(給与所得者の人数ー1) |
| 2割 | 43万円+(52万円×被保険者数) +(10万円×(給与所得者の人数ー1)) |
減免を申請するには、以下の書類を窓口に提出する必要があります。
- 各自治体から発行されている減免申請書
- 世帯の収入状況や保有資産がわかる書類
- (退職・失業が理由の場合)雇用保険受給者資格者証、給与証明書など
減免を申請する理由によって必要な書類が異なるため、一度役所の窓口で相談することがおすすめです。
住民税の減免制度
住民税の減免制度は、以下の条件に合えば適用される可能性があります。
- 失業した
- 生活保護を受給している
- 災害で被害を受けた
- 長期療養が必要
- 前年より所得が減額した
申請する場合は、収入状況申告書など各自治体が定めた書類を準備し、窓口に提出することが必要です。
また、申請理由によって提出書類が異なるほか、減免率や適用条件も各自治体によって異なります。
住民税の減免制度を利用する際は、一度窓口で相談するといいでしょう。
介護保険料の減額制度
介護保険料も場合によっては、減額制度が利用できます。
減額制度が利用できる主なケースは、以下のとおりです。
- 収入が大幅に減った
- 災害の被害を受けた
- 所得が低く生活が困窮している
また、各市町村が独自の減免措置制度を設けている場合もあり、その条件に該当すれば減額が受けられる可能性があります。
- 介護保険料を滞納していない
- 住民税を課せられている親族と同居中ではない など
減免の条件や制度の詳細、申請方法は各自治体によって異なるため、支払いが難しい場合は早めに窓口で相談しましょう。
税金・保険料を滞納するとどうなる?

「減免制度の申請、面倒だな」と思う人も多いでしょう。
もしかしたら、すでにさまざまな支払いを滞納している人もいるかもしれません。
しかし、税金・保険の滞納は絶対におすすめできません。
税金・保険を滞納するとどうなるのか、それぞれ詳しく解説します。
住民税の滞納による影響
住民税の滞納による影響は、主に以下の4つです。
- 延滞金が発生する
- 督促状が送られてくる
- 財産が差し押さえられる
- 社会的信用の損失
住民税の滞納金は、以下の計算式で算出され、滞納が続けば続くほど高額になっていきます。
- 延滞金=延滞した税額×延滞利率×延滞日数÷365日
- 延滞利率
2ヶ月以内:年7.3%、または特例基準割合+1%のいずれか低い方
2ヶ月以降:年14.6%、または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
特例基準割合とは、延滞金などを算出する際に用いられる国が定めた数値のこと。
毎年改正が行われ、令和7年度は「年1.4%」と定められています。
督促状を受け取っても納税しなければ、さらに何通かの催告書が届けられます。
そして、最終的には給料や預金口座などの財産の差し押さえが行われる仕組みです。
差し押さえられた後も納税しない場合は、差し押さえた財産が住民税に充てられます。
国民年金保険料の滞納による影響
国民年金保険料を滞納すると、延滞金が発生したり、督促状が届いたりするほか、最終的には財産の差し押さえが行われることもあります。
実際に、日本年金機構は年金未納者への対応を強化しており、令和5年度には13,243件もの差し押さえが執行されました。
ちなみに、国民年金保険料は令和7年度時点で毎月17,510円となっており、少しの期間滞納しただけでも、金額がかさんでしまいます。
さらに、滞納が続くと将来受け取れる年金の金額が減ってしまったり、条件によっては年金自体がもらえなくなる可能性もあります。
つまり、今の滞納が老後の生活にまで影響する恐れがあるのです。
不安なときは、未納のまま放置せず、早めに年金事務所や市区町村の窓口に相談することが大切です。
国民健康保険料の滞納による影響
国民健康保険料を滞納すると、住民税や年金と同じく延滞金が発生し、督促状が送られます。
長期に渡って滞納が続く場合、最終的に財産の差し押さえが行われる仕組みです。
また、保険給付も停止されます。
- 1年未満の滞納の場合:「短期保険証」に切り替わる
- 1年以上の滞納の場合:「資格証明書」に切り替わる
上記の場合、医療機関を受診した際の支払いは10割負担となり、後日窓口で申請して負担額が差し引かれる形です。
さらに、1年6ヶ月以上滞納が続くと、医療費の払い戻しが受けられなくなったり、高額療養費制度が利用できなくなるなどのリスクも出てきます。
困ったときは、放置せずに早めに役所に相談し、今の状況に合った支払い方法を一緒に考えてもらいましょう。
ニートと確定申告

「ニートに確定申告は必要ないでしょ」と思っている人も多いですよね。
しかし、ニートでも確定申告が必要なケースがあり、払い過ぎていた税金が返ってくることもあります。
ここからは、ニートでも確定申告が必要なケースと不要なケースについて、それぞれ詳しく解説していきます。
確定申告とは?
そもそも確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額を申告し、それに応じた所得税を計算する手続きです。
会社員であれば、会社が毎月源泉徴収を行い、年末調整によって納税額を調整しています。
しかし、自営業やフリーランス、給与所得以外の所得がある場合は、その所得を自分で申告する必要があります。
無職でも年金や不動産収入などの所得があれば、確定申告の対象です。
源泉徴収された税金や予定納税額がある場合は、その過不足が計算され、払い過ぎた分は還付金として返還されます。
ニートでも確定申告が必要なケース
ニートでも確定申告が必要なケースは、以下のとおりです。
- 退職してニートになった場合
- 医療費が多くかかった場合
- ふるさと納税をした場合
- 住宅ローン控除を受ける場合
- 不動産収入がある場合
- 年金を受給している場合
なかでも、年の途中で退職した場合、会社が年末調整を行なっていないため、確定申告をして所得税を再計算する必要があります。
この場合、年間の見込み所得が変動することで、税金の支払いが過剰になっていることが少なくありません。
確定申告をすることによって、多く支払った税金の還付を受けられる可能性が高いといえるでしょう。
また、年間の医療費が10万円を超えた場合やふるさと納税をした場合、住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告をすることで節税効果が得られます。
不動産収入や年金は所得税の課税対象となるため、必ず確定申告が必要です。
確定申告が不要なケース
1年間まったく収入がなかった場合、課税対象となる所得がないため、基本的に確定申告の義務はありません。
ただし、自分から「1年間無収入だったこと」を確定申告することで、翌年の国民健康保険料や住民税が軽減されることがあります。
というのも、ニートのように働いていない状態では、役所が本人の収入状況を正確に把握できないため、保険料や税額が高く算出されてしまうことがあるのです。
確定申告をして収入がなかったことを証明すれば、こうしたズレが正され、実際の生活状況に見合った金額に調整される可能性があるというわけです。
ニートの税金に関する疑問

働いていないのに税金の通知が届いたり、支払いを求められたりすると、不安や疑問を感じることもあるかもしれません。
ここでは、ニートの方からよく寄せられる税金に関する質問をQ&A形式でまとめました。
内容のおさらいも兼ねて、ひとつひとつ整理しながら確認してみましょう。
Q1: ニートでも本当に税金を払わなければなりませんか?
A. 状況によってはニートの状態でも税金や保険料を支払う必要がある場合があります。
たとえば、前の年にアルバイトなどで収入があった場合は、その年の住民税や所得税が発生する可能性があります。
また、働いていなくても国民年金保険料や国民健康保険料などは、年齢や扶養の状況によって支払い義務が生じます。
ただし、収入がない場合には、免除や減額、猶予の制度が用意されているため、いきなり「払えない=延滞」になってしまうわけではありません。
Q2: 収入が全くない場合でも支払う義務がある税金はありますか?
A. 収入が全くない場合でも、国民年金保険料や国民健康保険料、住民税の均等割は支払う義務があります。
- 国民年金保険料
20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があり、収入がなくても支払い対象。
ただし、免除や猶予の申請が可能。 - 国民健康保険料
扶養に入っていない場合、自分で加入して保険料を支払う必要がある。
前年の所得や世帯構成で決まるため、無収入でも高額になることがある。 - 住民税
前年の所得に応じて決まる所得割と、所得の金額に関わらず一律で決まる均等割がある。
均等割は、収入の有無に関わらず支払い義務がある。
Q3: 国民年金保険料は必ず払わないといけないの?免除される場合は?
A. 収入や生活状況によっては、国民年金保険料を免除または猶予してもらえる制度があります。
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある制度で、ニートや無職の人も原則として保険料の支払い対象になります。
ただし、収入が少ない場合や、経済的に支払いが困難な事情がある場合には、以下のような制度が利用できます。
- 免除制度
全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかが免除。
免除されても、将来の年金受給資格として期間はカウントされる。 - 納付猶予制度
20歳以上50歳未満の人で、前年所得が一定額以下の場合に利用できる制度。 - 学生納付特例制度
学生の場合、申請することで納付が猶予される。
いずれの制度も、申請しなければ適用されません。
「払えないから放置する」ではなく、「まずは相談・申請する」ことが大切です。
お住まいの市区町村の年金窓口や年金事務所で手続きができます。
Q4: 国民健康保険料は無職でも払う必要がありますか?保険料はいくらくらい?
A. 無職であっても扶養に入っていない場合は、自分で国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
国民健康保険は、会社の健康保険に加入していない人(自営業・アルバイト・無職など)が対象となる医療保険制度です。
保険料を納めていれば、医療機関を受診した際の自己負担は原則3割で済みます。
ちなみに、保険料の金額は住んでいる地域や前年の所得、世帯の人数によって異なります。
たとえば、無職でも前年にアルバイトなどで収入があったり、世帯内に収入のある人がいる場合は、保険料が高くなるということです。
ただし、所得が少ない人向けに軽減措置や分割払いの相談ができる制度もあります。
Q5: 住民税はいつ、どのように支払うのですか?前年無収入の場合は?
A. 住民税は、前年の所得に基づいて課税され、毎年6月頃に納税通知書が届きます。
通知書が届いたら、金融機関やコンビニ、自治体の窓口などで納付するのが一般的です。
自治体によっては、クレジットカード払いやバーコード決済が利用できる場合もあります。
前年無収入の場合でも、均等割(所得の金額に関わらず一律で決まる住民税)が課税されるため、一部の特例を除いて、支払いがゼロになることはありません。
Q6: 確定申告はニートでも必ずしないといけませんか?
A. ニートで収入がまったくない場合は、基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし、収入がないことを申告しておくことで、翌年度の国民健康保険料や住民税が軽減される可能性があります。
また、年の途中まで働いていて収入があった人が退職してニートになった場合は、年末調整がされていない可能性があるため、確定申告をすることで払いすぎた所得税が戻ってくることがあります。
ニートでも「収入の有無」や「前職の状況」によっては、確定申告をするとメリットが得られるケースがあるため、迷ったときは、税務署や役所に相談してみると安心です。
Q7: 親の扶養に入れば税金は一切かかりませんか?
A. 親の扶養に入っていても、すべての税金や保険料が免除されるわけではありません。
所得税や住民税、国民健康保険の負担は基本的にありませんが、国民年金保険料は本人に支払い義務が発生します。
Q8: 税金や保険料を滞納してしまった場合、どうすれば良いですか?
A. そのまま放置せず、できるだけ早く役所や担当窓口に相談することが大切です。
滞納を続けていると、延滞金が発生したり、最終的には財産の差し押さえといった厳しい対応につながることがあります。
また、国民健康保険の場合は、保険証が使えなくなり、医療費が全額自己負担になることもあるため、注意が必要です。
経済的に厳しい状況にある人のために、減免・猶予制度が用意されてるため、まずは早めに窓口で相談しましょう。
Q9: 減免制度を利用するための条件は厳しいですか?
A. 減免制度が利用できるかは、無収入である理由や世帯の収入状況などによって異なります。
たとえば、同じ「収入がない」状態でも、失業中なのか、家族の扶養に入っているのか、一人暮らしかなどで判断が変わるということです。
家族の扶養に入れず一人暮らしをしている場合などは、減免制度が利用できる可能性が高まります。
まずは役所に相談し、自分の状況を詳しく伝えてみましょう。
まとめ

働いていなくても、国民年金や国民健康保険、住民税など、思いがけず税金や保険料の支払いが発生することがあります。
「無職だから関係ない」と思っていたのに請求書が届いて驚いた…という方もいるかもしれません。
今回の記事の内容を簡単にまとめます。
ニートが支払う可能性のある税金・保険
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
- 住民税
- 介護保険料
- 所得税
税金・保険料を滞納すると
- 延滞金が発生する
- 督促状が届く
- 最終的に財産が差し押さえられる
▶︎減免・猶予制度が利用できるため、延滞する前に役所に相談する
ニートでも確定申告が必要なケース
- 退職してニートになった場合
- 医療費が多くかかった場合
- ふるさと納税をした場合
- 年金受給・不動産収入がある場合
▶︎収入がなくても確定申告することで、税金・保険料が減額されることがある
収入がない状態での税金・保険料の支払いは苦しいものがあります。
特に、家族の扶養に入らず一人暮らししている人にとっては、死活問題といえるでしょう。
しかし、収入がない人や支払いが難しい人のために、免除や減額、猶予といった制度がきちんと用意されています。
確定申告をすることで、節税できるケースも少なくありません。
「払えないから」と諦める前に、活用できる制度はないか、役所に相談してみることがおすすめです。
将来の安心につなげるためにも、不安や疑問をひとりで抱え込まず、まずは一歩踏み出してみましょう。