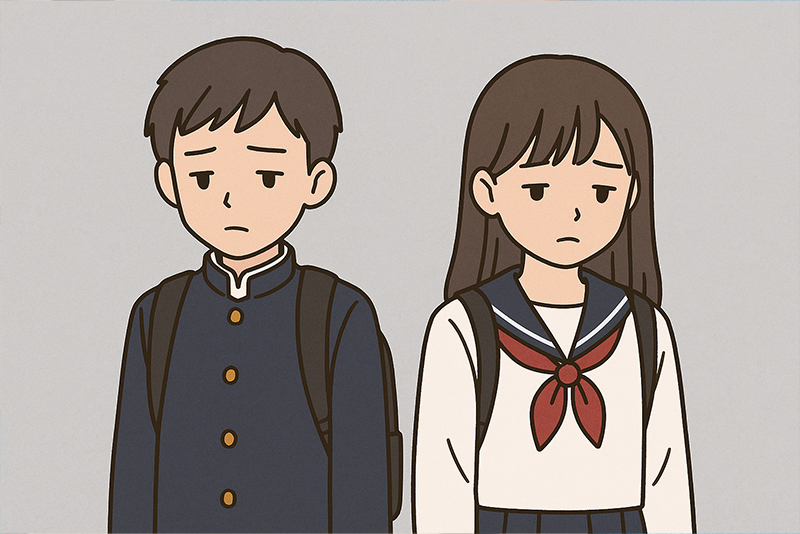
はじめに
不登校は、単なる登校拒否や “さぼり” の問題ではなく、多くの場合、子どもが抱える深い心の声や生活リズムの不調、学習や人間関係の困難、さらには社会構造や制度の課題が複雑に絡み合って生じる現象です。
近年、日本では不登校児童・生徒の数が過去最多を更新するなど、危機感が高まっています。
一方で、支援体制としては学校だけでなく、地域・民間・オンラインなど多様な場での取り組みが進んでおり、その可能性と課題が共存しています。
本記事では、不登校の定義と統計、支援の現状、課題、そして今後求められる方向性について整理し、家庭・学校・社会が協力して進んでいくべきロードマップを描きます。
1. 不登校とは?定義と現状
不登校の定義
「不登校」とは、一般に「病気や経済的理由を除き、心理的・社会的要因で年間30日以上欠席している状態」を指すことが多いです。文部科学省も同様の調査基準を設けており、不登校の児童・生徒の実態把握を行っています。
また、「長期欠席(90日以上)」など、欠席日数の幅で不登校を細かく分類するケースもあります。
最新の統計と傾向
小中学生(小~中学校):文部科学省の最新調査(令和5年度)で、小中学校における不登校児童・生徒数は34万6,482人。前年度比で47,434人増加し、11年連続で過去最多を更新しています。
小中高合計:2024年度(令和6年度)のデータでは、小中高合わせて42万1,752人の不登校が報告されました。
小中学生の在籍者に占める不登校率は、令和5年度時点で3.7%。
不登校理由:調査によれば、小中学生の不登校の主な相談内容は「学校生活への意欲低下(32.2%)」「不安・抑うつ(23.0%)」「生活リズムの不調(23.0%)」などで、多くの子どもが心理・情緒や生活の面でSOSを出していることがわかります。
支援の利用率:不登校の子どものうち、学校内・外の機関で相談・指導を受けている割合が非常に高まり、最新調査では95.8%にものぼるという報告もあります。
2. 不登校が増えている背景
心理・発達に関わる要因
心の不調やメンタルヘルス:不安・うつ、自己肯定感の低さ、ストレス耐久性の弱さなど、子ども自身の心理状態が不登校につながるケースが多くあります。
発達特性:発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)を抱える子どもは、学校の集団生活やルール、人間関係に適応しづらい面があるため、不登校になりやすいという指摘があります。
人間関係のストレス:いじめ、孤立、友人関係の悩みなどが強く影響し、不登校のきっかけとなることがあります。
生活リズム・ライフスタイルの変化
生活リズムの乱れ:夜更かしやスマホ・ゲーム利用、家庭での生活サイクルの乱れが、朝の登校を難しくする要因になっています。
モチベーションの低下:学習や授業に対する興味の低下、将来への不安などが、学校に行く意義を見いだせない子どもを増やしている可能性があります。
社会・制度的な要因
制度・支援の不十分さ:学校だけでは対応しきれない子どもに対して、地域や民間のサポート体制が地域差・情報格差として現れている。
学校の役割や在り方への疑問:学校という制度が「全ての子どもに合っているか」を再考する声が強まっており、既存の学校モデルがすべての子どもを包摂できていないという問題があります。
多様な学びの必要性:フリースクール・通信制・オンライン学習など、多様な選択肢がより強く求められています。
相談・支援窓口の偏在:地域によって専門家や相談機関の数や質に差があり、すべての子どもが平等に支援を受けられているとは言えません。
高校卒業支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「高校卒業支援プラン」は、不登校や引きこもりの方でも自分のペースで高卒資格を取得できるプログラムです。通信制高校を活用し、登校日数を抑えながら自宅での学習を進められ、教員免許を持つスタッフによる個別指導も受けられます。学習はレポート提出や動画教材、スクーリングを組み合わせて進め、必要に応じて大学受験対策も対応。資格取得や単位修得を柔軟に支援し、将来の進路の幅を広げます。自宅送迎や月額支払いにも対応しており、安心して学習を始められる環境が整っています。
3. 現在の不登校支援の取り組み
学校・行政による支援
スクールカウンセラーや教育相談:多くの公立学校でスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー(SSW)を配置し、子どもの心のケアや問題発見に努めています。
教育機会確保法(COCOLOプラン):「誰一人取り残されない学びの保障」に向けて、文部科学省は学びの多様化を推進。通信制・フリースクール・ICT学習など、学校以外の居場所づくりや出席扱い制度の整備を進めています。
相談・指導の制度強化:担任教師による継続的な相談や、学校内外の機関との連携を通じて、子どもが “戻る道” を探す支援がなされてきています。
政策対話・研究:日本学術会議などでは公開シンポジウムを開き、不登校現象と学校づくりの今後を議論しています。
民間・NPO・地域による支援
オンライン支援:NPO「カタリバ」などが提供するオンライン支援プログラムは、不登校の子どもに対して相談・学び・居場所を提供しています。
フリースクール・居場所づくり:地域に根ざした居場所(フリースクール・学習支援室など)で、通学とは異なるリズムで学べる場を提供。
予防プログラム:発達特性を持つ子どもたち向けの予防型支援プログラムも福祉団体などによって実施されており、早期のケアが進められています。
自主学習・ICT活用:自宅でのICT学習を “出席扱い” とする学校も増え、通学が難しい子どもにも学びの継続を保証する制度が広がっています。
4. 不登校支援の課題と問題点
地域差・情報格差
支援機関の配置不均衡:都市部にはNPOや専門相談機関が多い一方、地方や過疎地域では選択肢が非常に限られる。
情報へのアクセス不足:支援制度、居場所、相談窓口の情報が親・子どもに十分届いていないケースがあります。
支援の専門性・継続性の不足
専門スタッフ不足:スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、心理士など専門人材の配置は進んでいますが、学校あたり・地域あたりで見ればまだ十分とは言えず、対応が追いつかないケースもあります。
継続的支援の難しさ:一時的な相談や支援にとどまり、長期にわたる支援が難しい。子どもが支援を離れてしまうリスクがあります。
制度の限界:現在の出席扱いやICT出席制度は有効ですが、すべての子どもが制度を活用できるわけではなく、制度化・普及が途上です。
家庭・学校の理解・関係性の課題
保護者の理解不足:不登校をどう捉えるかという見方のズレがあると、支援を受け入れにくくなります。
学校側の対応力量:教員の多忙やスキル不足により、子どもの深い心理状態に気づけなかったり、適切な支援を提供しにくかったりする。
子どもの声の可視化:子どもの本人の希望・ニーズが十分に反映されず、支援プランが大人主導になってしまうケースもあります。
社会復帰・将来への支援の脆弱性
中・高卒後の進路不透明さ:不登校経験がある子どもの中には、高校卒業や進学・就労において困難を抱える人もいます。
孤立・経済的不安:家庭環境や経済状況が不安定だと、学校以外の場所(フリースクール・居場所)を継続利用するのが難しい。
社会的偏見:不登校経験に対する偏見や誤解が社会に根強く、子ども自身や保護者が声を出しづらい風潮があります。
5. 家庭・地域でできる支援 ― 実践とヒント
家庭での関わり方
子どもの話を聴く時間をつくる:子どもの不安や悩みを日常的に聞く場を持つ。無理に解決しようとせず、まずは受け止める姿勢が大切。
生活リズムの整備:起床・就寝時間、食事、スマホ・ゲームとの距離など、無理のない範囲でリズムを整える支援をする。
小さな目標設定:大きな「毎日登校」ではなく、「今日は10分教室に行ってみよう」「好きな教科だけ参加してみよう」など、小さな成功体験を積み重ねる。
家族の学び:親自身が不登校について学び、支援制度や相談先を把握しておく。地域の支援団体や専門家とのネットワークを築く。
地域・コミュニティでできること
居場所づくり:地域のNPO、ボランティア団体、自治体などと協力して、不登校の子どもが安心して過ごせる場所(学習支援・フリースクール・サロンなど)を設ける。
相談窓口の周知:地域の公民館、子育て支援センター、学校などで相談先を案内し、保護者・子どもに情報を届ける。
親同士の支援グループ:不登校経験のある親同士がつながり、情報交換や精神的支えを得られる場をつくる。
地域の教育機関との協働:学校・行政・民間が連携したフォーラムやワークショップを定期的に開催し、不登校支援の方針や具体的支援を共同で考える。
オンライン・ICTを活用した支援
オンライン相談・学習:対面が難しい子どもでもアクセスしやすいオンライン相談窓口や学習プログラムを活用。
ICT出席制度の活用:学校と協力し、自宅でのICT学習を “出席扱い” にする制度を利用する。
デジタル情報共有:地域・学校が支援制度やイベント、相談先をWEBサイトやSNSで発信し、子ども・保護者に届きやすくする。
高校卒業支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「高校卒業支援プラン」は、不登校や引きこもりの方でも自分のペースで高卒資格を取得できるプログラムです。通信制高校を活用し、登校日数を抑えながら自宅での学習を進められ、教員免許を持つスタッフによる個別指導も受けられます。学習はレポート提出や動画教材、スクーリングを組み合わせて進め、必要に応じて大学受験対策も対応。資格取得や単位修得を柔軟に支援し、将来の進路の幅を広げます。自宅送迎や月額支払いにも対応しており、安心して学習を始められる環境が整っています。
6. 今後の不登校支援の方向性
学校・制度の再構築
多様な学びの場をさらに拡充:通信制・フリースクール・オンラインスクールなど多様な学びの場の制度化・拡大を加速させる。
インクルーシブな学校づくり:不登校を経験する子どもも包み込める学校の在り方を見直す。
制度の柔軟化:出席扱い制度やICT出席、部分的参加など、子どもの状況に応じた柔軟な制度をさらに普及させる。
支援体制の強化と連携
専門人材の充実:スクールカウンセラー、心理士、ソーシャルワーカーなどの配置を増やし、どの学校・地域でも一定以上の支援が受けられるようにする。
行政・民間・学校の協働:地方自治体、NPO、学校が緊密に連携し、支援の “地域のエコシステム” を構築する。
政策の持続性:支援プログラムが一時的なプロジェクトに終わらず、継続可能な資金と制度設計を確立する。
子ども・家庭中心の支援設計
子どもの声を反映:支援策を設計する際に、子ども自身の希望やニーズを積極的に取り入れる。
早期発見と予防:心理・発達特性への理解を深め、未然に不登校に至るリスクを軽減する予防プログラムを学校や地域で普及させる。
進路支援と社会復帰:高校卒業後の進学・就労支援を強化し、不登校経験がある子どもに対しても将来の選択肢を確保する。
社会意識の変革
偏見・スティグマの軽減:不登校に対するネガティブなイメージを変えるための広報・教育活動を進める。
持続可能な政策の議論:不登校を “問題” とだけ見るのではなく、多様性の一つと捉え、教育制度全体の包摂性、柔軟性を議論する社会的枠組みを強化する。
結びに:一人ひとりに寄り添う支援を目指して
不登校は、単なる “学校に行かない” という現象以上のものです。そこには、子ども一人ひとりの心の叫び、家庭の葛藤、制度の限界、そして社会の価値観が交錯しています。
しかし同時に、私たちには支援の手段と希望もあります。学校、行政、NPO、地域、家庭、そして子ども自身が手を取り合って、多様な学びや居場所、相談の道を確保していくことができます。
子どもたちが安心して「行きたい場所」を選び、生き生きと学び、未来へつながる道を描けるように、支援者・保護者・教育関係者・地域住民を問わず、私たち一人ひとりが考え、行動を起こすことが求められています。







