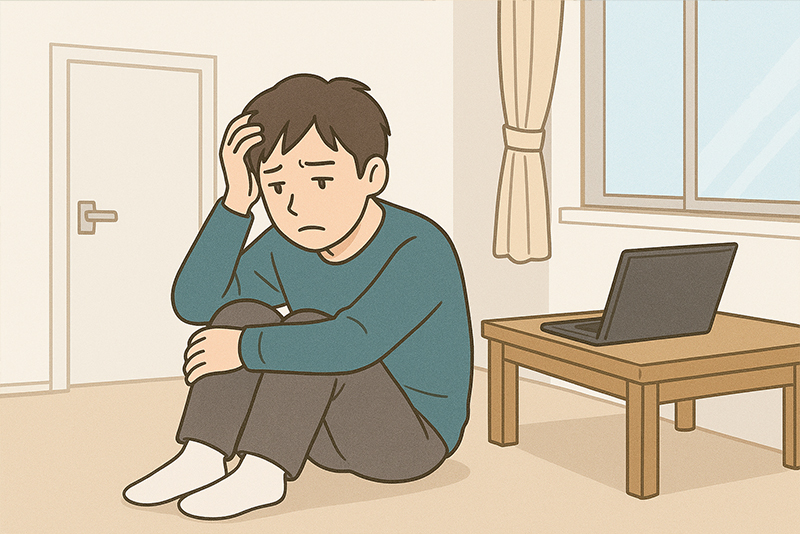
20代の引きこもりが増えている現状
近年、20代の引きこもりが深刻化しています。内閣府の調査によると、ひきこもり状態にある人のうち、20代の割合は年々増加しています。特に「一度社会に出たものの、退職をきっかけに家にこもってしまう」というケースが目立ちます。
高校や大学を卒業し、社会人としてスタートを切ったにもかかわらず、数か月〜数年で退職。その後、次の仕事に就けず、自信を失い、家に閉じこもる──。これは決して珍しいことではありません。
「社会人になれたのに」「ちゃんと働いていたのに」と、周囲が驚くことも多いですが、実際にはこのタイプの引きこもりは、内面に深い疲弊や孤立感を抱えています。
「一度社会に出た」人が引きこもる背景とは
20代で引きこもりになる背景には、思春期とは違う「社会との摩擦」があります。以下のような要因が重なりやすいのです。
① 理想と現実のギャップに直面する
学生時代には「働けば自立できる」と信じていたものの、実際には上司の叱責、人間関係のストレス、成果主義の厳しさに直面し、心が追いつかなくなることがあります。
② 真面目で責任感が強いタイプほど限界まで頑張る
「逃げるのは悪いこと」「もっと頑張らないと」と自分を追い込み、結果的に心身が疲弊。限界を超えたところで糸が切れるように出社できなくなり、そこから引きこもりに至るケースが多いです。
③ 職場での孤立・パワハラ・人間関係の問題
20代の若手社員は、まだ職場文化に慣れない中で「自分だけ浮いている」「誰にも相談できない」と感じがちです。職場でのいじめやパワハラも、引きこもりの大きな要因となっています。
④ 「やりたいことがわからない」空白感
大学卒業後に就職したものの、仕事にやりがいを感じられず退職。何をしたいのか分からないまま時間が過ぎ、自分を責めるうちに動けなくなる──そんな“迷子状態”になる20代も少なくありません。
典型的なケース例:20代前半男性Aさんの場合
Aさん(24歳)は大学を卒業後、営業職として就職しました。最初はやる気に満ちていたものの、ノルマが厳しく、上司からの叱責が続き、徐々に自信を失っていきます。
ある日、出勤前に動悸と吐き気が止まらなくなり、そのまま欠勤。数日休むつもりが、職場に戻れなくなってしまいました。退職後は「また失敗したらどうしよう」という不安が強く、求人サイトを見ることすら苦痛に。
家ではゲームやネット動画に没頭する日々が続き、次第に昼夜逆転。家族が声をかけても「放っておいて」と反発するようになりました。家族は心配しつつも、どのように関わればいいのか分からず、状況が長期化してしまいました。
このように、「社会に出た経験がある」からこそ、本人の中には「もう一度失敗したくない」「情けない」という感情が強く根を張ります。結果的に、外に出るエネルギーを失ってしまうのです。
典型的なケース例:20代後半女性Bさんの場合
Bさん(27歳)は専門学校卒業後、保育士として働いていました。子どもが好きで選んだ仕事でしたが、職場の人間関係や責任の重さに徐々に疲弊。先輩とのトラブルをきっかけに退職しました。
「少し休んだら次を探そう」と思っていたものの、気づけば数か月が経過。外に出るのが怖くなり、人と話すことも苦痛に感じるように。SNSでは友人が活躍している様子が目に入り、自分を責める気持ちが強くなっていきました。
家族は「せっかく資格があるんだから」と励ましたつもりでしたが、それがかえってプレッシャーになり、Bさんは部屋にこもるようになりました。
このように、女性の場合は「人間関係のストレス」や「他人と自分の比較」が引き金になることが多く、共感や安心を得られないと長期化する傾向があります。
就労自立支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「就労自立支援プラン」は、引きこもりや不登校、ニートの方が社会復帰と経済的自立を目指すための支援プログラムです。施設内での実務体験や大手企業との提携による就労体験を通じて、働く喜びやスキルを身につけられます。介護施設や飲食店など多様な職種での体験も可能で、生活拠点を整えながら無理なく社会との接点を持つことができます。自宅送迎や個別サポート、月額制の料金プランに対応しており、安心して学習と就労体験を始められる環境が整っています。
就職後の挫折が引き金になるメカニズム
20代の引きこもりの特徴は、「社会での失敗体験」が強烈に自己否定につながることです。
失敗=自分の全否定と感じやすい
社会人としての経験が浅い20代は、「失敗=自分はダメな人間だ」と結びつけやすいです。そのため、立ち直りに時間がかかり、再挑戦への恐怖が強くなります。
周囲の期待と本人の現実が合わない
親や周囲は「若いからやり直せる」と言いますが、本人にとっては「もう失敗した」「また怒られるのが怖い」という恐怖が先立ちます。このギャップが、さらに引きこもりを長引かせるのです。
心のエネルギーが枯渇している
焦って行動を促しても、本人には動く気力が残っていない場合があります。まずは「休むことを肯定する」期間が必要です。回復には“安全な居場所”が欠かせません。
家族がとるべき初期対応とNG対応
やってはいけない対応
・「いつまで家にいるつもり?」と責める
・「若いんだから働けるでしょ」と励ます
・無理やり外に出そうとする
これらはすべて逆効果です。本人の自己否定感を強め、「誰にも理解されない」という思いを深めてしまいます。
初期段階で大切なのは「理解」と「安心」
まずは、「あなたがつらい思いをしたことはわかる」と共感すること。解決を急がず、心を回復させることを優先します。焦る気持ちは当然ですが、回復には時間がかかることを受け入れることが大切です。
小さな行動を認める
・部屋から出てきた
・一緒に食事をした
・少し笑顔が見えた
これらを見逃さずに「うれしい」と伝えることで、本人の安心感が積み重なっていきます。
社会復帰に向けたステップと支援機関の活用
① 家庭内での信頼回復
焦らず、まずは家庭が「安全な居場所」になること。会話ができる関係を少しずつ取り戻すことが第一歩です。
② 外とのつながりを少しずつ
地域の相談窓口、ひきこもり支援センター、若者サポートステーションなどを活用しましょう。本人がすぐに行けない場合は、家族が相談して情報を得ることから始めても構いません。
③ 「働く前の準備期間」を設ける
引きこもり状態からいきなり就労は難しいです。まずは昼夜逆転を整えたり、生活リズムを取り戻すことから始めます。次に、フリースペースやボランティアなど、人と軽く関わる場を体験します。
④ 就労支援・社会参加への道
若者サポートステーションやNPOなどでは、面談・職業体験・カウンセリングなどを通じて「自分のペース」で社会復帰を支えます。家庭内だけで抱えず、外部の力を借りることが成功の鍵です。
「再スタート」を支える家族の関わり方
失敗を責めず、「やり直せる」ことを伝える
20代の引きこもりは、「失敗したら終わり」と感じやすい世代です。家族が「何度でもやり直せる」「あなたの味方でいる」と伝えることで、再挑戦への勇気を取り戻します。
親の期待を手放す勇気
「安定した職に就いてほしい」「普通の生活をしてほしい」と願うのは自然なことですが、親の理想を押しつけると、本人のプレッシャーになります。まずは「生きていてくれるだけでいい」と受け止めることが、最初の支えです。
家族自身もサポートを受ける
家族が孤立してしまうと、対応が厳しくなったり、感情的になったりします。自治体の家族会やカウンセリングを利用し、家族自身の心のケアも忘れないようにしましょう。
まとめ:失敗ではなく「次のステージ」へ
20代で社会に出たのち引きこもる人は、決して怠けているわけではありません。多くの場合、真面目で責任感が強く、頑張りすぎた結果、心が折れてしまったのです。
重要なのは、本人を責めることではなく、「もう一度立ち上がる力」を育てること。そのためには、家庭の中に「安心」「理解」「信頼」を取り戻すことが必要です。
引きこもりは「終わり」ではなく、人生を見つめ直す“中間地点”。失敗をきっかけに、自分らしい生き方を探す時間でもあります。
焦らず、一歩ずつ。
家族が寄り添いながら、20代の若者が再び社会とつながる日を信じて、支えていきましょう。







