- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
- 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
- (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
- 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
(引用:厚生労働省「障害福祉サービスについて」)
基本的には、企業やA型作業所での就労経験はあるが、障害や体力的な面で継続雇用が難しくなった方や、50歳以上、または障害などにより働くことが難しい方が対象です。
障害者手帳は必ずしも必要ではなく、障害福祉サービスの受給資格があることを証明する「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。
また、2025年10月からは「就労選択支援」という制度がスタートします。
これは、障害者本人に合った働き方や支援サービスを一緒に考えるためのサポートです。
就労アセスメント(就労能力評価)で、希望や能力、適正判断などが行われ、場合によってはB型作業所の利用が決まることもあります。
専門家があなたの家族に寄り添います。

「部屋から出てこない」「会話が成り立たない」そんな日々に疲れていませんか?
まだ諦めるには早すぎます。
私たち『らいさぽセンター』は多くの引きこもりの若者たちとそのご家族に寄り添ってきました。

まずは、引きこもり支援の専門家にあなたの話を聞かせてください。
A型作業所・就労移行支援との違い
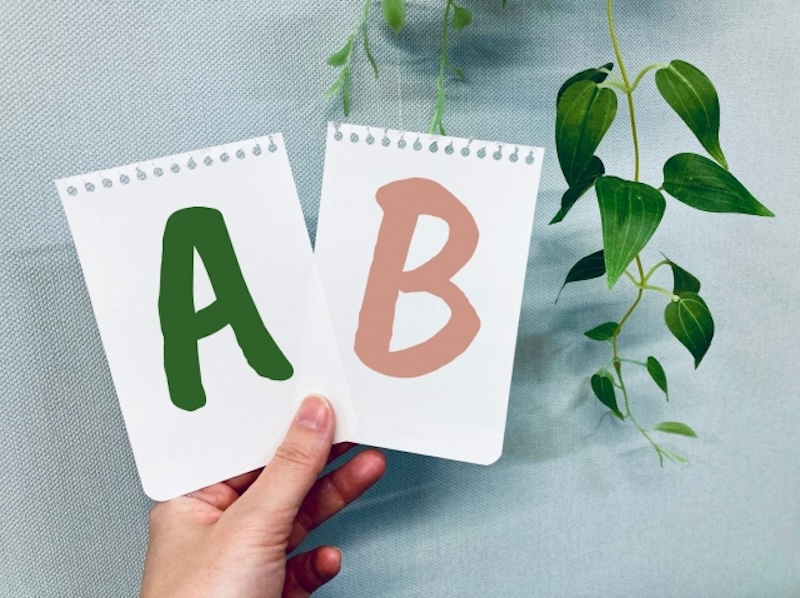
さまざまな福祉サービスがあり、どれが自分に合っているのか、判断に迷う人も少なくないはずです。
ここからは、A型作業所と就労移行支援との違いについて、それぞれ詳しく解説します。
- A型とB型の大きな違い”>A型とB型の大きな違い
- 工賃(給料)の違いはどれくらい?”>工賃(給料)の違いはどれくらい?
- 利用条件・期間の比較”>利用条件・期間の比較
- 支援の目的から見た選び方”>支援の目的から見た選び方
A型とB型の大きな違い”>A型とB型の大きな違い
A型とB型の大きな違いは「雇用契約を結ぶかどうか」です。
B型作業所では雇用契約を結ばないため、「工賃」という形で報酬が支払われますが、A型作業所では雇用契約を結び、「給料」が支払われます。
また、A型作業所では最低賃金が保障されるため、勤務時間や日数に条件があるのも大きな違いの1つです。
工賃(給料)の違いはどれくらい?”>工賃(給料)の違いはどれくらい?
B型作業所は、雇用契約を結ばないため、作業量や日数に応じた「成果報酬型」で工賃が支払われます。
厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、B型作業所の平均工賃は月23,053 円。
一番高い都道府県は、北海道の「26,675円」、一番低いのは沖縄県の「20,873円」となっています。
作業時間は利用者の体調や状況に合わせて調整できるため、1日1時間からでも作業可能です。
A型作業所は、雇用契約を結ぶため、各都道府県の最低賃金が保障されます。
厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、A型作業所の平均給料は月86,752円。
B型作業所と同じく、一番高い都道府県は、北海道の「87,766円」、一番低いのは沖縄県の「78,438円」となっています。
ノルマや残業はほとんどありませんが、決められた就業時間を安定的に出勤する体力や社会性が必要です。
また、勤務時間の長さによっては、働いた分の給料から雇用保険や施設の利用料、交通費などが引かれることもあります
| B型作業所 | A型作業所 | |
|---|---|---|
| 令和5年度の平均工賃 (賃金) | 月23,053 円 | 月86,752円 |
| 特徴 | 成果報酬型 | 時給制 |
| 出勤頻度 | 体調や状況に 合わせて調整 | 決められた就業時間に 合わせて出勤 |
利用条件・期間の比較”>利用条件・期間の比較
それぞれの作業所の利用条件や期間の違いは、以下のとおりです。
| B型作業所 | A型作業所 | 就労移行支援 | |
|---|---|---|---|
| 利用年齢 | 年齢制限なし | 18〜65歳未満 | 18〜65歳未満 |
| 対象者 | 長時間の就労が困難で 安定した雇用契約が 結べない人 | 通常の就労は難しいが ある程度安定して 働ける人 | 就労を目指して 職業訓練や就職活動を 行いたい人 |
| 利用期間 | 定めなし | 定めなし | 原則2年 |
支援の目的から見た選び方”>支援の目的から見た選び方
B型作業所・A型作業所・就労移行支援はそれぞれ、支援の目的が異なる福祉サービスです。
- B型作業所
働くことへの意欲を高めたり、やりがいを感じたりすることを目的に、軽作業などの訓練やリハビリを行う。 - A型作業所
企業就労に必要な知識やスキルを身につけながら、雇用契約のもとで実際に働く訓練を行う。 - 就労移行支援
企業への就職を目指し、職場に定着できるよう、実践的な訓練や就職活動のサポートを行う。
そのため、今自分が就労に向けてどの程度意欲や体力、知識、技術があるかによって、適切なサービスが異なります。
まずは生活リズムを整えながら働くことに慣れたい方は『B型作業所』、ある程度安定して働けるようになったら『A型作業所』へ、そして企業への就職を具体的に目指すなら『就労移行支援』を検討するといいでしょう。
B型作業所での仕事内容と1日の流れ

ここからは、B型作業所ではどんな仕事をするのか、代表的な作業の内容や1日のスケジュールについて解説します。
- どんな仕事をするの?代表的な作業”>どんな仕事をするの?代表的な作業
- B型作業所の1日のスケジュール例”>B型作業所の1日のスケジュール例
- 在宅でB型作業所を利用することはできる?”>在宅でB型作業所を利用することはできる?
- 通所日数や時間は自分で決められる?”>通所日数や時間は自分で決められる?
どんな仕事をするの?代表的な作業”>どんな仕事をするの?代表的な作業
B型作業所での主な作業は、以下のとおりです。
- 組み立て作業やパッキング・シール貼りなどの軽作業
- 簡単なデータ入力・ネットショップの出品などのパソコン作業
- 縫製・編み物などの手芸
- 農業やガーデニングなど
- ビルや施設の清掃など
具体的な作業内容は事業所によって異なりますが、利用者の障害や能力に合わせた作業を提供する形です。
B型作業所の1日のスケジュール例”>B型作業所の1日のスケジュール例
具体的なスケジュールは事業者や利用者によっても異なりますが、就労への意欲を高めることを目的としたB型作業所では、比較的こまめに休憩を取ることが多いです。
B型作業所の1日のスケジュールを見てみましょう。
◼️10:00〜10:15【朝礼】
連絡事項を確認したり、軽い運動を行ったりします。
◼️10:15〜11:00【午前の作業①】
午前中の作業を開始します。職員のサポートのもと、自分のペースで進めます。
◼️11:00〜11:15【小休憩】
小休憩を挟み、リフレッシュします。
◼️11:15〜12:00【午前の作業②】
再び作業スタート。午前中の作業を終えます。
◼️12:00〜13:00【昼休憩】
1時間の昼休憩です。各自の好きなスペースで昼食を取ります。
◼️13:00〜13:45【午後の作業①】
午後の作業をスタートします。
◼️13:45〜14:00【小休憩】
午後の小休憩を挟み、リフレッシュします。
◼️14:00〜14:45【午後の作業②】
作業を再開します。
◼️14:45〜15:00【小休憩】
疲労が溜まってくるタイミング。最後の小休憩を挟みます。
◼️15:00〜15:45【午後の作業③】
作業を再開したり、日誌に記入・後片付けを行います。
◼️15:45〜16:00【終礼】
掃除・終礼をして1日が終わります。
上記のように1日フルで作業する人もいれば、1日1時間程度の作業で終わる人など、その人の特性に合わせて作業時間は変動します。
また、作業中は自分のペースでゆっくりと進められることも特徴です。
始業時間や休憩の配分などは、各事業所によって異なります。
在宅でB型作業所を利用することはできる?”>在宅でB型作業所を利用することはできる?
B型作業所では、事業所に通うほかに、在宅で作業を行う『在宅就労』という形も可能です。
病気や障害で事業所に通うことが難しい場合や、人目が気になって作業に集中できないなどの特性を持っている場合は、在宅就労が認められる場合もあります。
たとえば、病気や障害の影響で外出が難しい場合や、人の多い環境では集中できないといった特性がある場合です。
作業内容は、パソコン入力やシール貼り、梱包などの軽作業が中心で、事業所と同じような内容を自宅で行いながら、就労に向けたリハビリとして取り組むことができます。
在宅でも無理なく自分のペースで続けられるため、少しずつ「働く感覚」を取り戻したい方におすすめです。
通所日数や時間は自分で決められる?”>通所日数や時間は自分で決められる?
B型作業所では、通所する日数や時間を、自分の体調や生活リズムに合わせて柔軟に決めることができます。
たとえば、「週に2~3日だけ」「午前中だけ通いたい」といった希望にも対応してもらえる場合が多く、無理のないペースで利用をスタートできることがメリットです。
体調が不安定な時期や、外出に慣れていない段階でも、少しずつ通うことで生活リズムを整えたり、働く習慣を身につけるきっかけになります。
まずは事業所と相談しながら、自分に合った通所スタイルを一緒に考えていくことが大切です。
B型作業所の工賃(お給料)

B型作業所では、作業の成果報酬として「工賃」が支払われます。
ここからは、B型作業所の工賃について、全国平均や計算方法をご紹介します。
- 工賃の全国平均はいくら?”>工賃の全国平均はいくら?
- 工賃はどうやって決まる?”>工賃はどうやって決まる?
- 障害年金と併給できる?収入の注意点”>障害年金と併給できる?収入の注意点
工賃の全国平均はいくら?”>工賃の全国平均はいくら?
B型作業所の工賃の全国平均は月23,053 円です。(厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について」参照)
この金額は年々上昇しており、10年前と比べておよそ1.5倍近くまで伸びています。
| 年度 | 工賃の全国平均金額/月 |
|---|---|
| 令和5年度 | 23,053円 |
| 令和4年度 | 17,031円 |
| 令和3年度 | 16,507円 |
| 令和2年度 | 15,776 円 |
| 令和元年度 | 16,369円 |
| 平成30年度 | 16,118 円 |
| 平成29年度 | 15,603 円 |
令和6年から平均金額の算出方法が変わったため、令和5年度の平均金額が大幅に上昇したほか、事業所ごとの工夫や支援体制の強化、自治体によるサポートなどが、工賃の底上げにつながっていると考えられます。
ただし、実際の金額は地域や作業内容、通所日数によって大きく異なるため、自分が利用を検討している事業所の工賃目安を事前に確認することも大切です。
工賃はどうやって決まる?”>工賃はどうやって決まる?
B型作業所の工賃は、行った作業で出た利益から経費を差し引いた金額が支払われます。
働いた時間などはカウントされず、作業内容や作業量から算出される成果報酬型です。
作業の種類によって報酬単価が設定されていることが多く、商品の売上や受注数によって月ごとの工賃額が変動することもあります。
そのため、工賃の金額は個人差があり、同じ作業所でも月2〜3万円を受け取っている人もいれば、数千円という人もいます。
工賃の内訳や支給方法については、事業所で説明を受けることができるので、気になる場合は遠慮なく相談してみましょう。
障害年金と併給できる?収入の注意点”>障害年金と併給できる?収入の注意点
障害年金とは、病気やケガなどにより働くことが難しい状態が続いている人を対象に支給される、公的な所得保障の制度です。
B型作業所やA型作業所などの就労継続支援による工賃や給料は、原則として障害年金に大きな影響を与える「収入」とはみなされません。
そのため、作業所に通いながらでも、障害年金を受け取り続けることが可能です。
通所中に障害年金が減額・支給停止となる場合は、収入以外の理由が考えられます。
また、作業所での活動内容や通所状況、医師の診断書の記載などによっては、「就労可能」と判断され、年金の等級が下がったり、一時的に支給が停止されたりするケースもあります。
これは収入額よりも、「どの程度働ける状態か」という点が重視されるためです。
年金を受給中の方がB型やA型作業所を利用する際は、年金制度との関係について、あらかじめ年金事務所や相談支援専門員に確認しておくといいでしょう。
B型作業所の利用方法と手続きの流れ

B型作業所を利用するには、事前に必要な手続きがあります。
ここでは、利用までの基本的な流れや相談先について、わかりやすく紹介します。
初めての方でも安心して進められるよう、順を追って確認していきましょう。
- 利用開始までの5つのステップ
- 必要な書類と手続き方法”>必要な書類と手続き方法
- 見学・体験はできる?利用前に確認したいこと”>見学・体験はできる?利用前に確認したいこと
- 利用料金はかかる?自己負担について”>利用料金はかかる?自己負担について
利用開始までの5つのステップ
利用開始までのステップは、以下のとおりです。
- 主治医にB型作業所を利用したいことを相談する
- 利用したい事業所を探す
- 役所の窓口で「障害福祉サービス受給者証」を申請する
- サービス等利用計画案を作成する
- B型作業所と契約して利用開始
まずは、主治医に「B型作業所を利用したい」と相談し、利用の可否や注意点についてアドバイスをもらいましょう。体調や通所の継続性をふまえたうえで、おすすめの事業所を紹介してもらえることもあります。
あわせて、市役所の障害福祉課やハローワークなどで情報収集をすることも可能です。事業所の見学や体験を通して、自分に合った場所を見つけることが大切です。
利用したい事業所が決まったら、お住まいの自治体にある「障害福祉窓口」で『障害福祉サービス受給者証』を申請します。この受給者証が交付されることで、正式に福祉サービスを利用する準備が整います。
その後、相談支援専門員と面談しながら、「サービス等利用計画案」を作成します。ここでは、現在抱えている課題や通所に向けた目標、どのような支援が必要かなどを整理します。
手続きがすべて整ったら、B型作業所と契約し、いよいよ利用開始です。不安な場合は、初めは週に1~2日から無理のないペースで始めることも可能です。利用開始後も、必要に応じて支援内容の見直しや調整が行えます。
必要な書類と手続き方法”>必要な書類と手続き方法
B型作業所を利用するには、お住まいの自治体にある障害福祉窓口で「障害福祉サービス受給者証」を申請する必要があります。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 障害者手帳(または主治医の意見書や診断書)
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 自立支援医療の受給者証(利用者のみ)
- お薬手帳
- 印鑑
障害福祉サービス受給者証を申請する際、職員との面談も実施されます。
- 現在の心身の健康状態について
- 治療中の病気や服用中の薬について
- 作業所に利用に対する意欲や心配事など
このような内容を質問されることが多いため、事前に回答を考えておくと、面談がスムーズに進むでしょう。
書類の提出・面談が終了したら、2週間から1ヶ月程度で障害福祉サービス受給者証が発行されます。
見学・体験はできる?利用前に確認したいこと”>見学・体験はできる?利用前に確認したいこと
B型作業所は、利用前の見学・体験が可能です。
見学や体験をしておくことで、作業内容・施設の雰囲気・職員の対応などを直接確認でき、「通えそうか」「無理なく続けられそうか」を判断しやすくなります。
- どんな作業があるか?(例:軽作業・清掃・パソコン作業など)
- 作業のペースや時間帯は自分に合っているか?
- 職員との距離感や支援の雰囲気はどうか?
- 通所にかかる交通手段・所要時間は無理がないか?
- 昼食の有無や利用料金についても確認を
事業所によって特徴や雰囲気が大きく異なるため、気になるところがあれば複数見学して比較するのがおすすめです。
見学や体験の希望は、直接事業所に連絡するか、相談支援専門員を通して調整してもらうとスムーズに行えます。
利用料金はかかる?自己負担について”>利用料金はかかる?自己負担について
B型作業所の利用には、原則として利用料の1割が自己負担となりますが、多くの方は実質無料またはごく少額で利用しています。
これは、世帯の所得に応じて「負担上限月額」が設けられているためです。
たとえば、生活保護を受けている世帯や住民税非課税の世帯であれば、自己負担は0円になるケースがあります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用料 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般世帯 | 市町村民税が課税されている世帯 | 9,300円または37,200円 (所得により異なる) |
また、作業に必要な材料費や昼食代、交通費などが別途かかる場合もあるため、気になる場合は役所の窓口や事業所で事前に確認しておきましょう。
自分に合ったB型作業所の選び方

B型作業所は事業所ごとに特徴や支援内容が異なります。
無理なく続けるためには、「どこでもいい」ではなく「自分に合った場所」を選ぶことが大切です。
ここでは、事業所を選ぶ際にチェックしておきたい7つのポイントをご紹介します。
- 作業内容と自分の適性・興味”>作業内容と自分の適性・興味
- 通いやすさと立地条件”>通いやすさと立地条件
- 事業所の雰囲気と支援方針”>事業所の雰囲気と支援方針
- 工賃の水準”>工賃の水準
- 自分の障害特性への理解度”>自分の障害特性への理解度
- ステップアップ支援の充実度”>ステップアップ支援の充実度
作業内容と自分の適性・興味”>作業内容と自分の適性・興味
シール貼り、袋詰め、パソコン作業など、作業内容は事業所によってさまざまです。
「やってみたい」「負担なくできそう」と思える内容かどうかを確認しておきましょう。
興味がある作業は、継続のモチベーションにもつながります。
通いやすさと立地条件”>通いやすさと立地条件
毎日・毎週通う場所だからこそ、自宅からの距離や交通手段、通所時間帯が自分に合っているかは重要なポイントです。
無理なく通えるかどうかを体験通所などで確認しておくと安心です。
事業所の雰囲気と支援方針”>事業所の雰囲気と支援方針
支援員との距離感や他の利用者との関係など、施設全体の雰囲気が自分に合うかどうかも大切です。
また、「自分のペースを尊重してくれるか」「就労に向けた支援方針が明確か」なども見学時に確認してみましょう。
工賃の水準”>工賃の水準
B型作業所では、工賃の金額は事業所ごとに異なります。
平均額や支給方法(時給・月額など)、成果に応じた変動があるかなどを事前にチェックし、自分の希望や生活スタイルに合っているかを見極めましょう。
自分の障害特性への理解度”>自分の障害特性への理解度
支援員があなたの障害特性や困りごとをきちんと理解し、配慮してくれるかは、安心して通ううえでとても重要です。
体調の波がある方や特定の配慮が必要な方は、見学時に率直に相談してみるのがおすすめです。
ステップアップ支援の充実度”>ステップアップ支援の充実度
B型作業所の中には、A型や一般就労へのステップアップをサポートしている事業所もあります。
将来的に「働けるようになりたい」と考えている場合は、就労支援プログラムの有無や実績も確認しておくとことがおすすめです。
B型作業所を利用するメリット・デメリット

B型作業所は、自分のペースで通所できる柔軟な支援が特徴です。
一方で、収入面や就職への距離感など、気になる点もあります。
ここでは、B型作業所を利用するうえでの代表的なメリット・デメリットを整理してご紹介します。
- メリット”>メリット
- デメリット”>デメリット
メリット”>メリット
B型作業所の最大のメリットは、無理のないペースで“働く感覚”を取り戻せることです。
週1日からの通所や短時間の作業にも対応しており、体調や気持ちに合わせて通所できます。
また、人との関わりを持つことで社会性やコミュニケーション力の向上が図れたり、毎日通所することで生活リズムの改善にもつながるため、社会復帰の第一歩としても有効です。
工賃が支払われる点も、自信ややりがいにつながります。
デメリット”>デメリット
一方で、工賃が最低賃金に満たないため、収入面での自立には限界があります。
また、一般就労への直接的な道につながる支援が少ない事業所もあり、ステップアップを目指す人には物足りなく感じることもあるかもしれません。
施設ごとの支援内容に差があるため、利用前の見学や確認はしっかりと行うことがおすすめです。
よくある質問
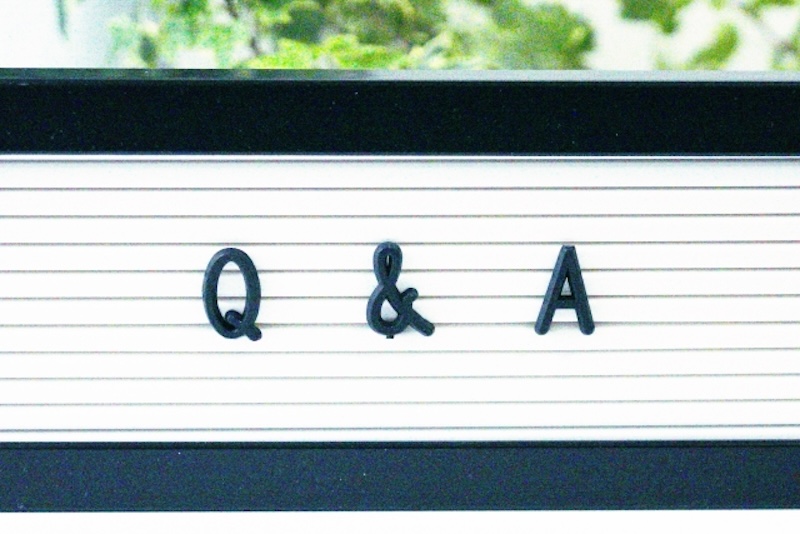
最後に、B型作業によくある質問をQ&A形式でご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- 障害者手帳がなくても利用できる?”>障害者手帳がなくても利用できる?
- B型からA型や一般就労へのステップアップは可能?”>B型からA型や一般就労へのステップアップは可能?
- 高齢者でも利用できる?年齢制限はある?”>高齢者でも利用できる?年齢制限はある?
- B型作業所と生活介護の違いは?”>B型作業所と生活介護の違いは?
- 精神障害や発達障害でも利用できる?”>精神障害や発達障害でも利用できる?
障害者手帳がなくても利用できる?”>障害者手帳がなくても利用できる?
A. 医師の意見書などがあれば、手帳がなくても利用できる場合があります。
B型作業所の利用には、障害者手帳が必須というわけではありません。
医師の診断書や意見書などで支援の必要性が認められれば、自治体の判断により利用が認められるケースもあります。
詳細はお住まいの市区町村に相談してみてください。
B型からA型や一般就労へのステップアップは可能?”>B型からA型や一般就労へのステップアップは可能?
A. B型作業所からA型や一般就労へステップアップすることは可能です。
体調が安定し、作業に慣れてくると、A型作業所への移行や一般企業への就職を目指す人もいます。
事業所によっては、就労に向けた支援や訓練プログラムが用意されている場合もあるため、最終的に就労を目指す人は、ステップアップ支援に力を入れている事業所を選ぶのもおすすめです。
無理なくステップアップしていくためには、支援員と相談しながら自分に合ったペースで準備を進めていきましょう。
高齢者でも利用できる?年齢制限はある?”>高齢者でも利用できる?年齢制限はある?
A. 原則として18歳以上であれば年齢制限はなく、高齢の方でも利用可能です。
B型作業所は年齢による上限は設けられていないため、65歳以上の方でも体力や希望に応じて利用することができます。
ただし、介護サービスの利用が適している場合は、そちらを案内されることもあります。
B型作業所と生活介護の違いは?”>B型作業所と生活介護の違いは?
A. 主な違いは「目的」と「活動内容」です。
B型作業所は“働くこと”を通じた自立支援が目的で、軽作業などを行います。
一方、生活介護は、日常生活の介助や機能訓練などが中心で、介護的なサポートが必要な方が対象です。
どちらが適しているかは、本人の状態に応じて判断されます。
精神障害や発達障害でも利用できる?”>精神障害や発達障害でも利用できる?
A. 精神障害や発達障害のある方も多く利用しています。
B型作業所は、身体障害・知的障害に限らず、精神障害や発達障害の方にも広く開かれた福祉サービスです。
配慮や支援体制が整っている事業所も多いため、特性に合った環境を選ぶことで、安心して通所することができます。
B型作業所で自分らしい働き方を見つけよう
B型作業所は、働くことに不安がある方や体調に波がある方でも、自分のペースで少しずつ「働く感覚」を取り戻すことができる場所です。
通所を通じて生活リズムが整い、人とのつながりややりがいも生まれます。
本記事の内容を簡単におさらいしていきましょう。
- B型作業所とは
▶︎雇用契約を結ばずに自分のペースで働く福祉サービスで、就労訓練や社会参加を目的としている。 - 利用条件
▶︎18歳以上で一般就労が難しい人が対象。障害者手帳がなくても医師の意見書などで利用可能な場合がある。 - 工賃の金額
▶︎工賃の全国平均は月約2.3万円(令和5年度)。作業内容や通所時間は柔軟に調整でき、在宅就労も可能。 - 就労と年金の両立が可能
▶︎障害年金との併給ができ、将来的にA型作業所や一般就労へのステップアップも目指せる。 - 事前の見学でミスマッチを防ぐ
▶︎利用前には事業所の見学や体験を通じて、自分に合った支援内容・雰囲気を確認することが大切。
はじめは小さな一歩でも、「できた」が積み重なれば、自信や新たな可能性につながります。
自分らしい働き方を見つけるために、まずは気になる作業所を見学したり、役所の窓口などで相談してみることから始めてみてくださいね。
ニート就労支援ページ
「B型作業所(就労継続支援B型)」とは、障害や難病などの理由で一般企業での就労が難しい方に向けた福祉サービスの一つです。雇用契約を結ばず、自分のペースで作業や活動に取り組める環境が整っており、特に体力に不安がある方や、就職経験があっても継続が難しかった方に適しています。
利用者は、軽作業や手工芸、農作業、パソコン業務などを通じて、生活リズムの安定や社会との接点を持つことができます。また、賃金にあたる「工賃」も支払われ、少額ながらも自立支援の一環となっています。
本記事では、B型作業所の具体的な仕組みや対象者、支援内容、工賃の実態、A型事業所との違い、そして利用までのステップを詳しく解説します。「福祉サービスを活用して無理なく社会参加したい」と考えている方にとって、B型作業所は重要な選択肢となるはずです。
- B型作業所とは
▶︎雇用契約を結ばずに自分のペースで働く福祉サービスで、就労訓練や社会参加を目的としている。 - 利用条件
▶︎18歳以上で一般就労が難しい人が対象。障害者手帳がなくても医師の意見書などで利用可能な場合がある。 - 工賃
▶︎工賃の全国平均は月約2.3万円(令和5年度)。作業内容や通所時間は柔軟に調整でき、在宅就労も可能。 - 就労と年金の両立が可能
▶︎障害年金との併給ができ、将来的にA型作業所や一般就労へのステップアップも目指せる。 - 事前の見学でミスマッチを防ぐ
▶︎利用前には事業所の見学や体験を通じて、自分に合った支援内容・雰囲気を確認することが大切。
B型作業所(就労継続支援B型)とは?

B型作業所(就労継続支援B型)は、障害や体調などの理由で一般就労が難しい人が、自分のペースで働くことができる福祉サービスです。
雇用契約が必要ないため、体調や生活状況に合わせて利用しやすく、無理なく社会とつながる第一歩になります。
ここでは、B型作業所の基本的な仕組みや特徴についてわかりやすく解説します。
- B型作業所の定義と目的”>B型作業所の定義と目的
- 「B型作業所」と「就労継続支援B型事業所」の違いは?”>「B型作業所」と「就労継続支援B型事業所」の違いは?
- 利用できる人の条件は?”>利用できる人の条件は?
>B型作業所の定義と目的
B型作業所について、厚生労働省では以下のように定義されています。
- 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
(引用元:厚生労働省「障害者福祉施設における就労支援の概要」)
わかりやすく解説すると、『障害や難病などの理由で一般企業での就労が難しい方を対象に、雇用契約を結ばずに働く機会や生産活動の場を提供する福祉サービス』です。
利用者は自分のペースで通所し、作業を行いながら知識や能力の向上を目指すことを目的としています。
「B型作業所」と「就労継続支援B型事業所」の違いは?”>「B型作業所」と「就労継続支援B型事業所」の違いは?
「B型作業所」と「就労継続支援B型事業所」という表記があり、どういった違いがあるのか気になっている人もいるかもしれません。
しかし、基本的に「B型作業所」と「就労継続支援B型事業所」は、どちらも指している場所やサービスは同じです。
正式名称として「就労継続支援B型事業所」、一般的な呼び名として「B型作業所」と表記してあると考えるとわかりやすいと思います。
利用できる人の条件は?”>利用できる人の条件は?
B型作業所(就労継続支援B型)を利用できる条件について、厚生労働省は以下のように定めています。
- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
- 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
- (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
- 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
(引用:厚生労働省「障害福祉サービスについて」)
基本的には、企業やA型作業所での就労経験はあるが、障害や体力的な面で継続雇用が難しくなった方や、50歳以上、または障害などにより働くことが難しい方が対象です。
障害者手帳は必ずしも必要ではなく、障害福祉サービスの受給資格があることを証明する「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。
また、2025年10月からは「就労選択支援」という制度がスタートします。
これは、障害者本人に合った働き方や支援サービスを一緒に考えるためのサポートです。
就労アセスメント(就労能力評価)で、希望や能力、適正判断などが行われ、場合によってはB型作業所の利用が決まることもあります。
専門家があなたの家族に寄り添います。

「部屋から出てこない」「会話が成り立たない」そんな日々に疲れていませんか?
まだ諦めるには早すぎます。
私たち『らいさぽセンター』は多くの引きこもりの若者たちとそのご家族に寄り添ってきました。

まずは、引きこもり支援の専門家にあなたの話を聞かせてください。
A型作業所・就労移行支援との違い
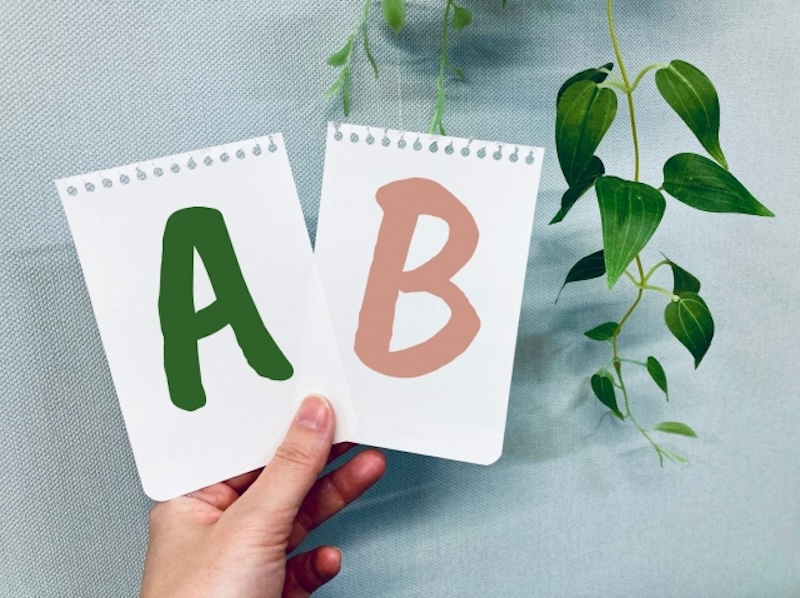
さまざまな福祉サービスがあり、どれが自分に合っているのか、判断に迷う人も少なくないはずです。
ここからは、A型作業所と就労移行支援との違いについて、それぞれ詳しく解説します。
- A型とB型の大きな違い”>A型とB型の大きな違い
- 工賃(給料)の違いはどれくらい?”>工賃(給料)の違いはどれくらい?
- 利用条件・期間の比較”>利用条件・期間の比較
- 支援の目的から見た選び方”>支援の目的から見た選び方
A型とB型の大きな違い”>A型とB型の大きな違い
A型とB型の大きな違いは「雇用契約を結ぶかどうか」です。
B型作業所では雇用契約を結ばないため、「工賃」という形で報酬が支払われますが、A型作業所では雇用契約を結び、「給料」が支払われます。
また、A型作業所では最低賃金が保障されるため、勤務時間や日数に条件があるのも大きな違いの1つです。
工賃(給料)の違いはどれくらい?”>工賃(給料)の違いはどれくらい?
B型作業所は、雇用契約を結ばないため、作業量や日数に応じた「成果報酬型」で工賃が支払われます。
厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、B型作業所の平均工賃は月23,053 円。
一番高い都道府県は、北海道の「26,675円」、一番低いのは沖縄県の「20,873円」となっています。
作業時間は利用者の体調や状況に合わせて調整できるため、1日1時間からでも作業可能です。
A型作業所は、雇用契約を結ぶため、各都道府県の最低賃金が保障されます。
厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、A型作業所の平均給料は月86,752円。
B型作業所と同じく、一番高い都道府県は、北海道の「87,766円」、一番低いのは沖縄県の「78,438円」となっています。
ノルマや残業はほとんどありませんが、決められた就業時間を安定的に出勤する体力や社会性が必要です。
また、勤務時間の長さによっては、働いた分の給料から雇用保険や施設の利用料、交通費などが引かれることもあります
| B型作業所 | A型作業所 | |
|---|---|---|
| 令和5年度の平均工賃 (賃金) | 月23,053 円 | 月86,752円 |
| 特徴 | 成果報酬型 | 時給制 |
| 出勤頻度 | 体調や状況に 合わせて調整 | 決められた就業時間に 合わせて出勤 |
利用条件・期間の比較”>利用条件・期間の比較
それぞれの作業所の利用条件や期間の違いは、以下のとおりです。
| B型作業所 | A型作業所 | 就労移行支援 | |
|---|---|---|---|
| 利用年齢 | 年齢制限なし | 18〜65歳未満 | 18〜65歳未満 |
| 対象者 | 長時間の就労が困難で 安定した雇用契約が 結べない人 | 通常の就労は難しいが ある程度安定して 働ける人 | 就労を目指して 職業訓練や就職活動を 行いたい人 |
| 利用期間 | 定めなし | 定めなし | 原則2年 |
支援の目的から見た選び方”>支援の目的から見た選び方
B型作業所・A型作業所・就労移行支援はそれぞれ、支援の目的が異なる福祉サービスです。
- B型作業所
働くことへの意欲を高めたり、やりがいを感じたりすることを目的に、軽作業などの訓練やリハビリを行う。 - A型作業所
企業就労に必要な知識やスキルを身につけながら、雇用契約のもとで実際に働く訓練を行う。 - 就労移行支援
企業への就職を目指し、職場に定着できるよう、実践的な訓練や就職活動のサポートを行う。
そのため、今自分が就労に向けてどの程度意欲や体力、知識、技術があるかによって、適切なサービスが異なります。
まずは生活リズムを整えながら働くことに慣れたい方は『B型作業所』、ある程度安定して働けるようになったら『A型作業所』へ、そして企業への就職を具体的に目指すなら『就労移行支援』を検討するといいでしょう。
B型作業所での仕事内容と1日の流れ

ここからは、B型作業所ではどんな仕事をするのか、代表的な作業の内容や1日のスケジュールについて解説します。
- どんな仕事をするの?代表的な作業”>どんな仕事をするの?代表的な作業
- B型作業所の1日のスケジュール例”>B型作業所の1日のスケジュール例
- 在宅でB型作業所を利用することはできる?”>在宅でB型作業所を利用することはできる?
- 通所日数や時間は自分で決められる?”>通所日数や時間は自分で決められる?
どんな仕事をするの?代表的な作業”>どんな仕事をするの?代表的な作業
B型作業所での主な作業は、以下のとおりです。
- 組み立て作業やパッキング・シール貼りなどの軽作業
- 簡単なデータ入力・ネットショップの出品などのパソコン作業
- 縫製・編み物などの手芸
- 農業やガーデニングなど
- ビルや施設の清掃など
具体的な作業内容は事業所によって異なりますが、利用者の障害や能力に合わせた作業を提供する形です。
B型作業所の1日のスケジュール例”>B型作業所の1日のスケジュール例
具体的なスケジュールは事業者や利用者によっても異なりますが、就労への意欲を高めることを目的としたB型作業所では、比較的こまめに休憩を取ることが多いです。
B型作業所の1日のスケジュールを見てみましょう。
◼️10:00〜10:15【朝礼】
連絡事項を確認したり、軽い運動を行ったりします。
◼️10:15〜11:00【午前の作業①】
午前中の作業を開始します。職員のサポートのもと、自分のペースで進めます。
◼️11:00〜11:15【小休憩】
小休憩を挟み、リフレッシュします。
◼️11:15〜12:00【午前の作業②】
再び作業スタート。午前中の作業を終えます。
◼️12:00〜13:00【昼休憩】
1時間の昼休憩です。各自の好きなスペースで昼食を取ります。
◼️13:00〜13:45【午後の作業①】
午後の作業をスタートします。
◼️13:45〜14:00【小休憩】
午後の小休憩を挟み、リフレッシュします。
◼️14:00〜14:45【午後の作業②】
作業を再開します。
◼️14:45〜15:00【小休憩】
疲労が溜まってくるタイミング。最後の小休憩を挟みます。
◼️15:00〜15:45【午後の作業③】
作業を再開したり、日誌に記入・後片付けを行います。
◼️15:45〜16:00【終礼】
掃除・終礼をして1日が終わります。
上記のように1日フルで作業する人もいれば、1日1時間程度の作業で終わる人など、その人の特性に合わせて作業時間は変動します。
また、作業中は自分のペースでゆっくりと進められることも特徴です。
始業時間や休憩の配分などは、各事業所によって異なります。
在宅でB型作業所を利用することはできる?”>在宅でB型作業所を利用することはできる?
B型作業所では、事業所に通うほかに、在宅で作業を行う『在宅就労』という形も可能です。
病気や障害で事業所に通うことが難しい場合や、人目が気になって作業に集中できないなどの特性を持っている場合は、在宅就労が認められる場合もあります。
たとえば、病気や障害の影響で外出が難しい場合や、人の多い環境では集中できないといった特性がある場合です。
作業内容は、パソコン入力やシール貼り、梱包などの軽作業が中心で、事業所と同じような内容を自宅で行いながら、就労に向けたリハビリとして取り組むことができます。
在宅でも無理なく自分のペースで続けられるため、少しずつ「働く感覚」を取り戻したい方におすすめです。
通所日数や時間は自分で決められる?”>通所日数や時間は自分で決められる?
B型作業所では、通所する日数や時間を、自分の体調や生活リズムに合わせて柔軟に決めることができます。
たとえば、「週に2~3日だけ」「午前中だけ通いたい」といった希望にも対応してもらえる場合が多く、無理のないペースで利用をスタートできることがメリットです。
体調が不安定な時期や、外出に慣れていない段階でも、少しずつ通うことで生活リズムを整えたり、働く習慣を身につけるきっかけになります。
まずは事業所と相談しながら、自分に合った通所スタイルを一緒に考えていくことが大切です。
B型作業所の工賃(お給料)

B型作業所では、作業の成果報酬として「工賃」が支払われます。
ここからは、B型作業所の工賃について、全国平均や計算方法をご紹介します。
- 工賃の全国平均はいくら?”>工賃の全国平均はいくら?
- 工賃はどうやって決まる?”>工賃はどうやって決まる?
- 障害年金と併給できる?収入の注意点”>障害年金と併給できる?収入の注意点
工賃の全国平均はいくら?”>工賃の全国平均はいくら?
B型作業所の工賃の全国平均は月23,053 円です。(厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について」参照)
この金額は年々上昇しており、10年前と比べておよそ1.5倍近くまで伸びています。
| 年度 | 工賃の全国平均金額/月 |
|---|---|
| 令和5年度 | 23,053円 |
| 令和4年度 | 17,031円 |
| 令和3年度 | 16,507円 |
| 令和2年度 | 15,776 円 |
| 令和元年度 | 16,369円 |
| 平成30年度 | 16,118 円 |
| 平成29年度 | 15,603 円 |
令和6年から平均金額の算出方法が変わったため、令和5年度の平均金額が大幅に上昇したほか、事業所ごとの工夫や支援体制の強化、自治体によるサポートなどが、工賃の底上げにつながっていると考えられます。
ただし、実際の金額は地域や作業内容、通所日数によって大きく異なるため、自分が利用を検討している事業所の工賃目安を事前に確認することも大切です。
工賃はどうやって決まる?”>工賃はどうやって決まる?
B型作業所の工賃は、行った作業で出た利益から経費を差し引いた金額が支払われます。
働いた時間などはカウントされず、作業内容や作業量から算出される成果報酬型です。
作業の種類によって報酬単価が設定されていることが多く、商品の売上や受注数によって月ごとの工賃額が変動することもあります。
そのため、工賃の金額は個人差があり、同じ作業所でも月2〜3万円を受け取っている人もいれば、数千円という人もいます。
工賃の内訳や支給方法については、事業所で説明を受けることができるので、気になる場合は遠慮なく相談してみましょう。
障害年金と併給できる?収入の注意点”>障害年金と併給できる?収入の注意点
障害年金とは、病気やケガなどにより働くことが難しい状態が続いている人を対象に支給される、公的な所得保障の制度です。
B型作業所やA型作業所などの就労継続支援による工賃や給料は、原則として障害年金に大きな影響を与える「収入」とはみなされません。
そのため、作業所に通いながらでも、障害年金を受け取り続けることが可能です。
通所中に障害年金が減額・支給停止となる場合は、収入以外の理由が考えられます。
また、作業所での活動内容や通所状況、医師の診断書の記載などによっては、「就労可能」と判断され、年金の等級が下がったり、一時的に支給が停止されたりするケースもあります。
これは収入額よりも、「どの程度働ける状態か」という点が重視されるためです。
年金を受給中の方がB型やA型作業所を利用する際は、年金制度との関係について、あらかじめ年金事務所や相談支援専門員に確認しておくといいでしょう。
B型作業所の利用方法と手続きの流れ

B型作業所を利用するには、事前に必要な手続きがあります。
ここでは、利用までの基本的な流れや相談先について、わかりやすく紹介します。
初めての方でも安心して進められるよう、順を追って確認していきましょう。
- 利用開始までの5つのステップ
- 必要な書類と手続き方法”>必要な書類と手続き方法
- 見学・体験はできる?利用前に確認したいこと”>見学・体験はできる?利用前に確認したいこと
- 利用料金はかかる?自己負担について”>利用料金はかかる?自己負担について
利用開始までの5つのステップ
利用開始までのステップは、以下のとおりです。
- 主治医にB型作業所を利用したいことを相談する
- 利用したい事業所を探す
- 役所の窓口で「障害福祉サービス受給者証」を申請する
- サービス等利用計画案を作成する
- B型作業所と契約して利用開始
まずは、主治医に「B型作業所を利用したい」と相談し、利用の可否や注意点についてアドバイスをもらいましょう。体調や通所の継続性をふまえたうえで、おすすめの事業所を紹介してもらえることもあります。
あわせて、市役所の障害福祉課やハローワークなどで情報収集をすることも可能です。事業所の見学や体験を通して、自分に合った場所を見つけることが大切です。
利用したい事業所が決まったら、お住まいの自治体にある「障害福祉窓口」で『障害福祉サービス受給者証』を申請します。この受給者証が交付されることで、正式に福祉サービスを利用する準備が整います。
その後、相談支援専門員と面談しながら、「サービス等利用計画案」を作成します。ここでは、現在抱えている課題や通所に向けた目標、どのような支援が必要かなどを整理します。
手続きがすべて整ったら、B型作業所と契約し、いよいよ利用開始です。不安な場合は、初めは週に1~2日から無理のないペースで始めることも可能です。利用開始後も、必要に応じて支援内容の見直しや調整が行えます。
必要な書類と手続き方法”>必要な書類と手続き方法
B型作業所を利用するには、お住まいの自治体にある障害福祉窓口で「障害福祉サービス受給者証」を申請する必要があります。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 障害者手帳(または主治医の意見書や診断書)
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 自立支援医療の受給者証(利用者のみ)
- お薬手帳
- 印鑑
障害福祉サービス受給者証を申請する際、職員との面談も実施されます。
- 現在の心身の健康状態について
- 治療中の病気や服用中の薬について
- 作業所に利用に対する意欲や心配事など
このような内容を質問されることが多いため、事前に回答を考えておくと、面談がスムーズに進むでしょう。
書類の提出・面談が終了したら、2週間から1ヶ月程度で障害福祉サービス受給者証が発行されます。
見学・体験はできる?利用前に確認したいこと”>見学・体験はできる?利用前に確認したいこと
B型作業所は、利用前の見学・体験が可能です。
見学や体験をしておくことで、作業内容・施設の雰囲気・職員の対応などを直接確認でき、「通えそうか」「無理なく続けられそうか」を判断しやすくなります。
- どんな作業があるか?(例:軽作業・清掃・パソコン作業など)
- 作業のペースや時間帯は自分に合っているか?
- 職員との距離感や支援の雰囲気はどうか?
- 通所にかかる交通手段・所要時間は無理がないか?
- 昼食の有無や利用料金についても確認を
事業所によって特徴や雰囲気が大きく異なるため、気になるところがあれば複数見学して比較するのがおすすめです。
見学や体験の希望は、直接事業所に連絡するか、相談支援専門員を通して調整してもらうとスムーズに行えます。
利用料金はかかる?自己負担について”>利用料金はかかる?自己負担について
B型作業所の利用には、原則として利用料の1割が自己負担となりますが、多くの方は実質無料またはごく少額で利用しています。
これは、世帯の所得に応じて「負担上限月額」が設けられているためです。
たとえば、生活保護を受けている世帯や住民税非課税の世帯であれば、自己負担は0円になるケースがあります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用料 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般世帯 | 市町村民税が課税されている世帯 | 9,300円または37,200円 (所得により異なる) |
また、作業に必要な材料費や昼食代、交通費などが別途かかる場合もあるため、気になる場合は役所の窓口や事業所で事前に確認しておきましょう。
自分に合ったB型作業所の選び方

B型作業所は事業所ごとに特徴や支援内容が異なります。
無理なく続けるためには、「どこでもいい」ではなく「自分に合った場所」を選ぶことが大切です。
ここでは、事業所を選ぶ際にチェックしておきたい7つのポイントをご紹介します。
- 作業内容と自分の適性・興味”>作業内容と自分の適性・興味
- 通いやすさと立地条件”>通いやすさと立地条件
- 事業所の雰囲気と支援方針”>事業所の雰囲気と支援方針
- 工賃の水準”>工賃の水準
- 自分の障害特性への理解度”>自分の障害特性への理解度
- ステップアップ支援の充実度”>ステップアップ支援の充実度
作業内容と自分の適性・興味”>作業内容と自分の適性・興味
シール貼り、袋詰め、パソコン作業など、作業内容は事業所によってさまざまです。
「やってみたい」「負担なくできそう」と思える内容かどうかを確認しておきましょう。
興味がある作業は、継続のモチベーションにもつながります。
通いやすさと立地条件”>通いやすさと立地条件
毎日・毎週通う場所だからこそ、自宅からの距離や交通手段、通所時間帯が自分に合っているかは重要なポイントです。
無理なく通えるかどうかを体験通所などで確認しておくと安心です。
事業所の雰囲気と支援方針”>事業所の雰囲気と支援方針
支援員との距離感や他の利用者との関係など、施設全体の雰囲気が自分に合うかどうかも大切です。
また、「自分のペースを尊重してくれるか」「就労に向けた支援方針が明確か」なども見学時に確認してみましょう。
工賃の水準”>工賃の水準
B型作業所では、工賃の金額は事業所ごとに異なります。
平均額や支給方法(時給・月額など)、成果に応じた変動があるかなどを事前にチェックし、自分の希望や生活スタイルに合っているかを見極めましょう。
自分の障害特性への理解度”>自分の障害特性への理解度
支援員があなたの障害特性や困りごとをきちんと理解し、配慮してくれるかは、安心して通ううえでとても重要です。
体調の波がある方や特定の配慮が必要な方は、見学時に率直に相談してみるのがおすすめです。
ステップアップ支援の充実度”>ステップアップ支援の充実度
B型作業所の中には、A型や一般就労へのステップアップをサポートしている事業所もあります。
将来的に「働けるようになりたい」と考えている場合は、就労支援プログラムの有無や実績も確認しておくとことがおすすめです。
B型作業所を利用するメリット・デメリット

B型作業所は、自分のペースで通所できる柔軟な支援が特徴です。
一方で、収入面や就職への距離感など、気になる点もあります。
ここでは、B型作業所を利用するうえでの代表的なメリット・デメリットを整理してご紹介します。
- メリット”>メリット
- デメリット”>デメリット
メリット”>メリット
B型作業所の最大のメリットは、無理のないペースで“働く感覚”を取り戻せることです。
週1日からの通所や短時間の作業にも対応しており、体調や気持ちに合わせて通所できます。
また、人との関わりを持つことで社会性やコミュニケーション力の向上が図れたり、毎日通所することで生活リズムの改善にもつながるため、社会復帰の第一歩としても有効です。
工賃が支払われる点も、自信ややりがいにつながります。
デメリット”>デメリット
一方で、工賃が最低賃金に満たないため、収入面での自立には限界があります。
また、一般就労への直接的な道につながる支援が少ない事業所もあり、ステップアップを目指す人には物足りなく感じることもあるかもしれません。
施設ごとの支援内容に差があるため、利用前の見学や確認はしっかりと行うことがおすすめです。
よくある質問
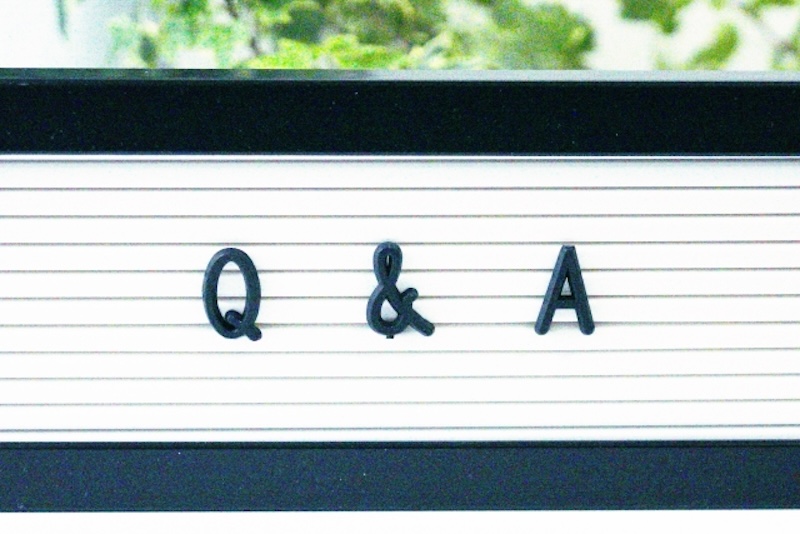
最後に、B型作業によくある質問をQ&A形式でご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- 障害者手帳がなくても利用できる?”>障害者手帳がなくても利用できる?
- B型からA型や一般就労へのステップアップは可能?”>B型からA型や一般就労へのステップアップは可能?
- 高齢者でも利用できる?年齢制限はある?”>高齢者でも利用できる?年齢制限はある?
- B型作業所と生活介護の違いは?”>B型作業所と生活介護の違いは?
- 精神障害や発達障害でも利用できる?”>精神障害や発達障害でも利用できる?
障害者手帳がなくても利用できる?”>障害者手帳がなくても利用できる?
A. 医師の意見書などがあれば、手帳がなくても利用できる場合があります。
B型作業所の利用には、障害者手帳が必須というわけではありません。
医師の診断書や意見書などで支援の必要性が認められれば、自治体の判断により利用が認められるケースもあります。
詳細はお住まいの市区町村に相談してみてください。
B型からA型や一般就労へのステップアップは可能?”>B型からA型や一般就労へのステップアップは可能?
A. B型作業所からA型や一般就労へステップアップすることは可能です。
体調が安定し、作業に慣れてくると、A型作業所への移行や一般企業への就職を目指す人もいます。
事業所によっては、就労に向けた支援や訓練プログラムが用意されている場合もあるため、最終的に就労を目指す人は、ステップアップ支援に力を入れている事業所を選ぶのもおすすめです。
無理なくステップアップしていくためには、支援員と相談しながら自分に合ったペースで準備を進めていきましょう。
高齢者でも利用できる?年齢制限はある?”>高齢者でも利用できる?年齢制限はある?
A. 原則として18歳以上であれば年齢制限はなく、高齢の方でも利用可能です。
B型作業所は年齢による上限は設けられていないため、65歳以上の方でも体力や希望に応じて利用することができます。
ただし、介護サービスの利用が適している場合は、そちらを案内されることもあります。
B型作業所と生活介護の違いは?”>B型作業所と生活介護の違いは?
A. 主な違いは「目的」と「活動内容」です。
B型作業所は“働くこと”を通じた自立支援が目的で、軽作業などを行います。
一方、生活介護は、日常生活の介助や機能訓練などが中心で、介護的なサポートが必要な方が対象です。
どちらが適しているかは、本人の状態に応じて判断されます。
精神障害や発達障害でも利用できる?”>精神障害や発達障害でも利用できる?
A. 精神障害や発達障害のある方も多く利用しています。
B型作業所は、身体障害・知的障害に限らず、精神障害や発達障害の方にも広く開かれた福祉サービスです。
配慮や支援体制が整っている事業所も多いため、特性に合った環境を選ぶことで、安心して通所することができます。
B型作業所で自分らしい働き方を見つけよう
B型作業所は、働くことに不安がある方や体調に波がある方でも、自分のペースで少しずつ「働く感覚」を取り戻すことができる場所です。
通所を通じて生活リズムが整い、人とのつながりややりがいも生まれます。
本記事の内容を簡単におさらいしていきましょう。
- B型作業所とは
▶︎雇用契約を結ばずに自分のペースで働く福祉サービスで、就労訓練や社会参加を目的としている。 - 利用条件
▶︎18歳以上で一般就労が難しい人が対象。障害者手帳がなくても医師の意見書などで利用可能な場合がある。 - 工賃の金額
▶︎工賃の全国平均は月約2.3万円(令和5年度)。作業内容や通所時間は柔軟に調整でき、在宅就労も可能。 - 就労と年金の両立が可能
▶︎障害年金との併給ができ、将来的にA型作業所や一般就労へのステップアップも目指せる。 - 事前の見学でミスマッチを防ぐ
▶︎利用前には事業所の見学や体験を通じて、自分に合った支援内容・雰囲気を確認することが大切。
はじめは小さな一歩でも、「できた」が積み重なれば、自信や新たな可能性につながります。
自分らしい働き方を見つけるために、まずは気になる作業所を見学したり、役所の窓口などで相談してみることから始めてみてくださいね。





