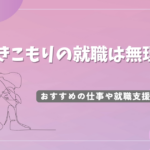はじめに
以下では「引きこもり」と「暴力」の問題について、原因から解決までを整理していきます。
1. 引きこもりと暴力の関係とは
「引きこもり」とは、6か月以上にわたって自宅に閉じこもり、社会との接点を持たない状態を指します。近年では中高生だけでなく、20代、30代、さらには40代以上の「中高年の引きこもり」も社会問題化しています。
内閣府の調査によると、全国で100万人以上の人がひきこもり状態にあると推計されており、その一部には家庭内での暴力を伴うケースが存在します。
一般的に「引きこもりは静かに部屋で過ごす人」というイメージがありますが、実際には暴力や威圧的な行為が同居家族に向けられることも少なくありません。特に親や同居家族に対して、言葉の暴力、物を壊す行為、さらには身体的な暴力へと発展することがあります。
これは本人の「性格が悪い」からではなく、背景に精神的問題や社会的孤立が絡み合っていることを理解する必要があります。
2. 引きこもりから暴力につながる原因
精神的な要因
引きこもりの多くは、うつ病、不安障害、発達障害、統合失調症などの精神的問題が関連しています。強いストレスや不安感を抱えていると、感情をうまくコントロールできず、衝動的に暴力に訴えることがあります。
また「自分の状況を理解してもらえない」という孤独感も攻撃性につながります。
家族関係や育った環境の影響
幼少期からの家庭環境も大きく影響します。過度な干渉、過保護、または過度な期待は、本人の自己肯定感を下げ「親は敵だ」という認識を持たせることがあります。結果として、最も身近である家族に怒りが集中するのです。
社会からの孤立とストレス
人との交流がなくなると、考え方が偏りやすくなります。小さな出来事を「攻撃された」と受け止めてしまい、家族に反発するケースもあります。孤立が続けば続くほどストレスが蓄積し、暴力行為が増す傾向にあります。
経済的不安と将来への焦り
特に30代以降になると「働いていない自分」「将来どうやって生活していくのか」という焦燥感が高まりやすくなります。その不安を言葉にできないとき、暴力という形で表面化することが少なくありません。
3. 家庭で起こる暴力の実態
引きこもりによる暴力は、家庭内で繰り返し発生しやすいのが特徴です。
親への暴力
生活費や物を要求する際に拒否されると手を上げる、注意されると逆上して殴るなど
兄弟姉妹への影響
物音や怒鳴り声に常に怯え、家庭内で安心できなくなる
心理的暴力
物を壊す、壁を叩く、怒鳴ることで家族を支配しようとする
長期化のリスク
一度始まった暴力が常態化し、日常生活そのものが恐怖に支配される
被害を受けている家族は「誰にも言えない」「恥ずかしい」と抱え込みがちですが、それが問題をさらに悪化させる要因になります。
4. 暴力を放置することの危険性
暴力を放置すると状況は改善するどころか、むしろ悪化します。
家族関係の崩壊
家庭内の信頼が壊れ、家族が別居や離散を選ばざるを得なくなる
本人の孤立と悪循環
暴力を繰り返すことで本人も自己嫌悪に陥り、さらに外部と関われなくなる
犯罪・事件化のリスク
家庭内の暴力がエスカレートし、傷害事件や警察沙汰につながることもある
つまり「家庭内だから大丈夫」ではなく「家庭内だからこそ危険」なのです。
5. 法律的な観点:家庭内暴力と法的対応の違い
法律面から見ると、引きこもりによる暴力も放置できない重大な問題です。
DV防止法
配偶者や恋人間の暴力を規制する法律。親子間の暴力は対象外だが、警察相談の窓口は活用可能
児童虐待防止法
18歳未満の子どもへの親の暴力を対象とする。成人した子どもから親への暴力は対象外
刑法(暴行罪・傷害罪・脅迫罪)
家庭内であっても、暴力や威嚇は通常の犯罪として扱われる
実際に家庭内での暴力が警察に通報され、逮捕に至るケースもあります。家族だからといって犯罪が免除されるわけではありません。
また、自治体によっては「家庭内暴力相談窓口」が設けられており、被害者である家族が安全に暮らすためのサポートを受けることも可能です。
6. 解決に向けたステップ
家族ができる初期対応
- 暴力が起きたら安全を第一に考え、物理的に距離を取る
- 被害の状況を記録(日記や写真)として残す
- 決して一人で抱え込まず、第三者に相談する
専門機関への相談
- ひきこもり地域支援センター:本人・家族双方を支援
- 精神保健福祉センター:心の健康相談や医療につなぐ役割
- 医療機関(心療内科・精神科):症状の診断と治療
医療・カウンセリングの活用
精神的疾患がある場合は医療的介入が必要不可欠です。薬物療法や認知行動療法などを通じて、感情のコントロールを取り戻すことができます。
社会復帰支援
- NPO団体による訪問支援
- 居場所づくり(交流スペースや作業所)
- ステップアップ型の就労支援
本人が少しずつ外の世界と関われるような仕組みを整えることが大切です。
7.引きこもりの就労支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校は、静岡県御殿場市にある全寮制の支援施設で、ひきこもりや不登校、ニートの方々の就労支援に力を入れています。施設内での実務体験や資格取得サポートを通じて、自信を持って社会復帰できるよう支援。快適な生活環境と24時間体制のサポートで安心して取り組めます。
地域の行政や企業と連携し、多くの実績を持つらいさぽセンターで、あなたも一歩踏み出しませんか?まずはお気軽にお問い合わせください。
8. 家族が心を守るために
暴力の被害にあっている家族もまた支援が必要です。
- 家族会や自助グループに参加して同じ悩みを共有する
- カウンセリングを受け、自分の心のケアを優先する
- 「自分のせいではない」と意識し、罪悪感を持たない
- 必要であれば一時的に距離を取ることも考える
家族の心身が消耗してしまえば、支援を続けることはできません。自分自身を守ることが結果的に本人への支援にもつながります。
9. まとめ
引きこもりと暴力は、社会全体で考えるべき重要な課題です。
「家庭の問題」として隠されがちですが、放置すれば家族も本人もより深刻な状況に陥ります。
- 暴力を軽視せず、早めに相談する
- 専門機関や法律の力も活用する
- 家族の安全と安心を最優先にする
- 本人の社会復帰を長期的に支援する
この問題に直面した家族は決して一人ではありません。全国には支援窓口や団体が存在し、解決に向けた道筋があります。
引きこもりと暴力に向き合うためには、家族が「助けを求めてよい」と思えることが最初の一歩なのです。
ひきこもり就労支援ページ

お子さんの未来のために
私たちが全力でサポートします。

一歩を踏み出しましょう。
当サービスを通じて、
新しい人生の道が開けます。
さあ、今すぐお問い合わせください。
初回相談は無料で、
専門スタッフが丁寧にご案内します。
この機会をお見逃しなく。