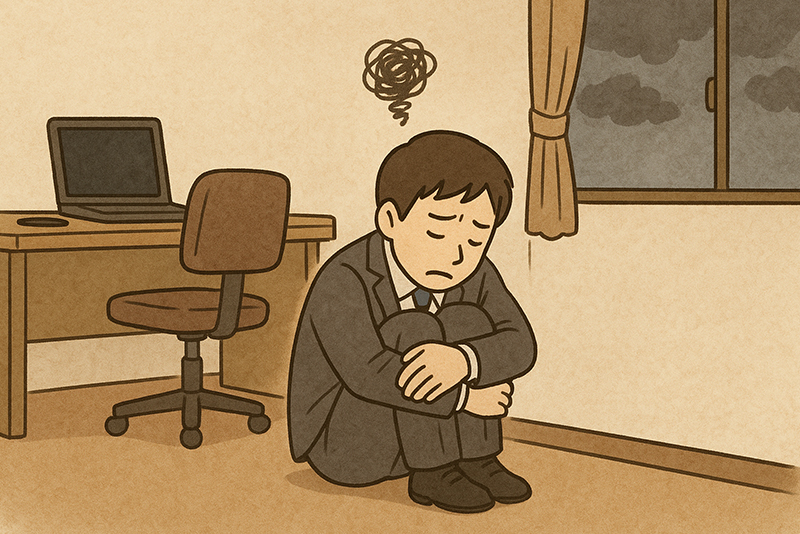
はじめに:増え続ける「社会人の引きこもり」という現実
「引きこもり」という言葉は、以前は主に若者や学生を指すものでした。しかし現在は、20代後半〜50代、さらには定年後の高齢層まで、幅広い世代に広がっています。内閣府の調査でも、40代以上の引きこもりが増加しており、「社会人になってから引きこもる人」も珍しくありません。
就職後の人間関係のトラブル、過労やメンタル不調、職場での孤立感などが引き金となり、退職後に社会との関わりを断ってしまうケースが増えています。社会人の引きこもりは、単なる「怠け」ではなく、長期間にわたる心の疲労や挫折感の結果です。
この記事では、社会人の引きこもりに焦点を当て、その原因・心理的背景・支援の方法・回復への具体的ステップを、本人・家族・支援者それぞれの視点から解説します。
なぜ社会人が引きこもりになるのか
職場ストレスや人間関係の摩擦
社会人が引きこもりになるきっかけの多くは、職場でのストレスです。上司や同僚との人間関係のトラブル、過剰なノルマ、パワーハラスメント、成果主義のプレッシャーなどが心身を追い詰めます。真面目で責任感の強い人ほど、自分を責め続けて限界を超えてしまう傾向があります。
過労・メンタル不調からの退職
長時間労働や睡眠不足、慢性的な疲労によって心がすり減り、「出勤できない」「体が動かない」という状態に陥る人も多いです。そのまま休職・退職し、回復しないまま家にこもってしまうケースが少なくありません。
コロナ禍以降の孤立と在宅化
コロナ禍によるテレワークの定着は、一方で「人との接触機会の減少」を招きました。人と話さなくても仕事ができる環境が続くうちに、対人不安が強まり、次第に外出やコミュニケーション自体が苦痛になるケースも見られます。
「もう働けない」と感じる心理的要因
社会人の引きこもりには、「挫折」「喪失」「無力感」といった心理的背景があります。失業や人間関係の失敗を経験し、「自分には価値がない」と思い込むことで、再挑戦するエネルギーを失ってしまうのです。
就労自立支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「就労自立支援プラン」は、引きこもりや不登校、ニートの方が社会復帰と経済的自立を目指すための支援プログラムです。施設内での実務体験や大手企業との提携による就労体験を通じて、働く喜びやスキルを身につけられます。介護施設や飲食店など多様な職種での体験も可能で、生活拠点を整えながら無理なく社会との接点を持つことができます。自宅送迎や個別サポート、月額制の料金プランに対応しており、安心して学習と就労体験を始められる環境が整っています。
社会人引きこもりの特徴と課題
年齢による支援の狭間にいる
若年層には「若者サポートステーション」などの支援制度がありますが、30代・40代になると対象外になるケースが多く、支援の空白が生まれています。この「どこにも属せない」感覚が、さらなる孤立を招きます。
経済的不安と生活リズムの崩壊
仕事を失うと、経済的な不安が大きなストレスになります。生活費を親に頼る場合、家庭内の緊張関係も悪化しやすくなります。また、昼夜逆転など生活リズムの乱れも進行し、社会復帰が難しくなる悪循環に陥ることがあります。
家族との関係悪化と依存
家族が支えようとするほど、本人が「責められている」と感じて反発するケースもあります。親子の会話が途絶え、互いに傷つけ合う関係になると、回復の糸口が見えづらくなります。
自己肯定感の低下と孤立
社会人の引きこもりでは、「もう自分には社会で通用しない」という自己否定感が強いです。自信を失った状態では、外に出ること自体が恐怖になります。この心理的障壁を乗り越えるには、時間と理解が必要です。
家族・周囲ができる初期対応
無理に働かせようとしない
「早く働かないと」「このままでどうするの」といった言葉は、本人をさらに追い詰めます。焦らず、「今の状態でもあなたの存在は大切だよ」というメッセージを伝えることが第一歩です。
否定せず、現状を受け止める
「なぜできないの?」ではなく、「今はしんどいんだね」と寄り添う姿勢を示しましょう。理解されていると感じることで、本人の中に「信頼」が生まれ、少しずつ心を開いてくれるようになります。
会話の再開から始める
無理に話を引き出す必要はありません。挨拶や天気の話など、短い会話を積み重ねることで信頼を築きます。「おはよう」「ご飯できたよ」といった声かけが、孤立を防ぐ第一歩になります。
生活リズムを整えるサポート
食事や睡眠など、生活の基本を一緒に見直すことも大切です。朝食を一緒に食べる、夜は照明を落とすなど、環境を整えることで少しずつ社会的リズムを取り戻せます。
本人ができる「小さな第一歩」
朝起きて日光を浴びる
日光を浴びることは、体内時計をリセットし、気持ちを前向きにする効果があります。まずは「午前中にカーテンを開ける」だけでも構いません。
1日1回、誰かと話す
家族、コンビニの店員、SNSでのやり取り——どんな形でも「人と関わる」ことが回復への第一歩です。孤立を防ぎ、社会への再接続を助けます。
オンラインや在宅の活動から始める
いきなり職場復帰を目指すのではなく、在宅でできる仕事やボランティア、オンライン学習など、「社会とのつながり」を持つ練習から始めましょう。
できたことを「記録」する
「今日は朝起きられた」「外に出た」など、小さな達成をノートに書き残すことで、自己肯定感を回復できます。積み重ねが自信へと変わっていきます。
再就職・社会復帰支援の活用法
就労移行支援事業所を利用する
障害やメンタル不調を抱える人が、社会復帰を目指すための訓練や支援を受けられる公的サービスです。生活リズムの安定から職場実習まで、段階的に支援してもらえます。
地域若者サポートステーション(サポステ)
39歳までの方を対象に、就職相談や職業体験などのサポートを提供しています。心理的なサポートも充実しており、安心して一歩を踏み出せる環境です。
ハローワークや生活支援センター
就労だけでなく、生活費・住居支援なども含めた総合相談が可能です。引きこもりが長期化している場合は、福祉的な支援を受けることも選択肢に入ります。
民間・NPOによる社会復帰プログラム
最近では、引きこもり支援に特化したNPOやカウンセリング機関も増えています。居場所づくりやピアサポート(同じ経験を持つ仲間同士の支援)は、社会復帰のきっかけになりやすいです。
就労自立支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「就労自立支援プラン」は、引きこもりや不登校、ニートの方が社会復帰と経済的自立を目指すための支援プログラムです。施設内での実務体験や大手企業との提携による就労体験を通じて、働く喜びやスキルを身につけられます。介護施設や飲食店など多様な職種での体験も可能で、生活拠点を整えながら無理なく社会との接点を持つことができます。自宅送迎や個別サポート、月額制の料金プランに対応しており、安心して学習と就労体験を始められる環境が整っています。
メンタル面のケアと専門的サポート
うつ・適応障害を併発するケースが多い
社会人の引きこもりでは、うつ病や適応障害が背景にある場合が少なくありません。「やる気が出ない」「人に会いたくない」が続くときは、心療内科やカウンセラーへの相談を検討しましょう。
カウンセリングで心の整理をする
第三者に話すことで、自分でも気づかなかった気持ちを整理できます。家族に話せないことも、専門家なら安心して話せることがあります。
焦らず治すことが社会復帰の近道
無理に「元に戻ろう」とするより、まずは「休む」「立ち止まる」時間を大切にしましょう。心が回復すれば、自然と次のステップが見えてきます。
家族も支援を受けることが大切
家族会やピアサポートへの参加
引きこもりの家族を支援する会では、同じ悩みを持つ親たちが情報交換や相談を行っています。「自分だけじゃない」と感じることで、親の孤立を防げます。
親のストレスケアも忘れずに
親自身が疲弊してしまうと、子どもに余裕をもって接することが難しくなります。趣味や外出、カウンセリングなど、自分をいたわる時間を持ちましょう。
支援のネットワークを活用する
行政、医療、福祉、地域支援団体が連携してサポートする仕組みもあります。困ったときに相談できる人や機関をリスト化しておくと安心です。
まとめ:一人で頑張らなくていい。「つながる」ことが回復の第一歩
社会人の引きこもりは、「誰にでも起こり得る現代の心の問題」です。大切なのは、「怠け」と決めつけずに、本人が抱える痛みに寄り添うこと。そして、家族・社会・専門機関がつながり、支え合うことです。
今日できることは、小さな一歩で十分です。朝起きる、話をする、相談してみる。その積み重ねが、再び社会と関わる力になります。孤立の先に希望はあります。焦らず、自分のペースで、歩き出していきましょう。







